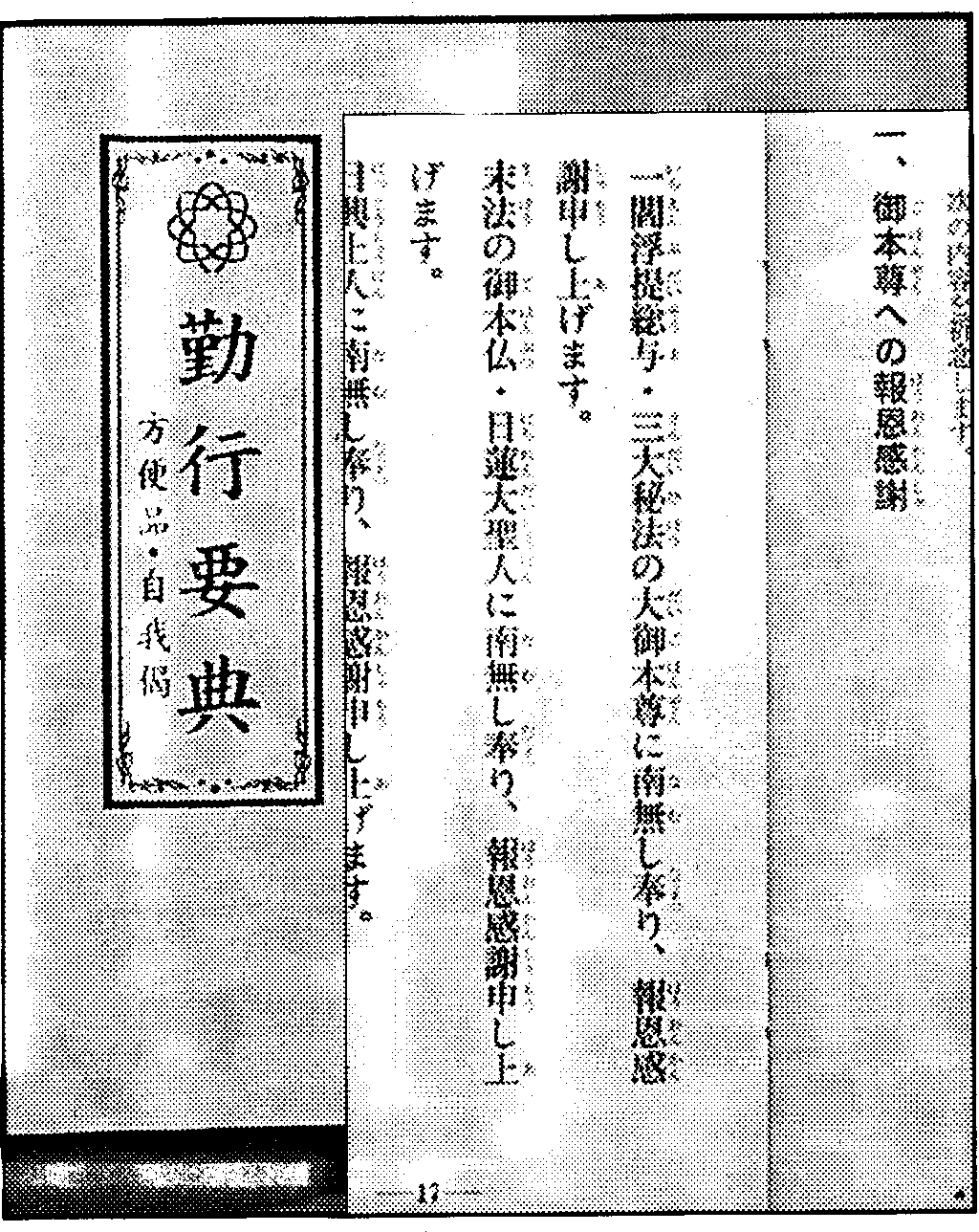意義を違えた観念文(2座)
―「一閻浮提総与の御本尊」とボカシたが…―
―それは本門戒壇の大御本尊の御事だ!―
(『慧妙』H26.7.1)
学会版経本には
「一、御本尊への報恩感謝 一閻浮提総与(いちえんぶだいそうよ)・三大秘法の大御本尊に南無し奉(たてまつ)り、報恩感謝申し上げます」
と書かれている。
さて、まず学会のいう「一閻浮提総与」ということについて考えてみよう。
最初に、誰が一閻浮提総与と言ったのか、はっきりさせておく。
学会員は、大聖人が御書等において述べられている、と思うのだろうが、そうではない。59世日亨上人が
「近年荒木翁が戒壇本尊は未来の満天下の一切衆生に授与せられたものであるから総与の御本尊と云ふべきと主張した」(『大日蓮』T12.1)
と示されるように、当時の法華講総講頭であった荒木清勇氏が初めて使用した言葉なのである。
そもそも、これがどういう意味かを理解しているだろうか。
学会では、
「一閻浮提総与だから、自分たち全ての民衆に与えられた御本尊である」というくらいに考えているようだが、「一閻浮提総与の御本尊」とは、一人一人の僧俗が御下附いただく御本尊とは異なり、広宣流布の暁(あかつき)に全世界の信仰の根本道場となる本門戒壇に安置され、全世界のすべての人々が礼拝する、根源の御本尊である。
しかして、この御本尊が何処(いずこ)に在(ましま)すか、といえば、富士大石寺に安置し奉る弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊こそが、一閻浮提総与の大御本尊であり、その証拠に、この大御本尊の脇書には「本門戒壇」と認(したた)められているのである。
かつては学会も
「弘安2年10月12日の大御本尊は一閻浮提総与の大御本尊であり、本門戒壇の大御本尊であります」(『大白蓮華』71号)
と言い、はっきり「弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊」が一閻浮提総与の本尊である、としていた。
しかるに、現今の学会は、経本の中から「本門戒壇」の文言を削除し、「一閻浮提総与」という言葉を、曖昧(あいまい)に、都合よく使って、会員達を欺(あざむ)いているのである。
なおまた、日蓮正宗勤行要典における「2座本尊供養」の意義は、久遠元初の本仏・本法の当体が本門戒壇の大御本尊であり、この最勝絶対の大御本尊の御威光倍増・御利益広大・御報恩謝徳を観念する中に、信心の2字をもって自ずと我等も成仏得道せしめ給えとの観念も含在しているのである。
学会では、難しいことを行じたり観念することは現代に即さない、と言う。そして、その故に勤行を改変し、観念文を改変したという。
我々末法の凡夫の立場としては、大聖人が
「有信無解とて解(げ)はなくとも信心あるものは成仏すべし」(御書P1461)
とお示しのごとく、その表わすところの深い意義を解することができなくても、信心をもって行ずべきであり、『譬喩品』に、
「大智舎利弗すら猶(なお)信を以て入ることを得たり」
と説かれるごとく、信をもって慧に代え、成仏を願うことが肝要なのである。
御隠尊日顕上人は
「『経文という、文字によって誰にでも確認出来る教えのみを認めるのが正しい仏法の大原則だ』などの主張は、まさに仏法の深意を蔑(ないがし)ろにする摧尊入卑(さいそ
んにゅうひ)の偏見です。大聖人の仏法は従浅至深、そんな簡単なものではありません。そこに創価学会の仏法に対する浅識と軽視と不信が存するのであります」
と御指南されている。
つまり経文でもそうであるが、信をもって智慧に代えることが肝要で、解らないことがあれば省略する、などということは、浅識(せんしき)と軽善(きょうぜん)と不信が存するのである。
あくまでも、大聖人からの血脈相伝の御法主上人に信をとり、化儀を行なうことが大切である。
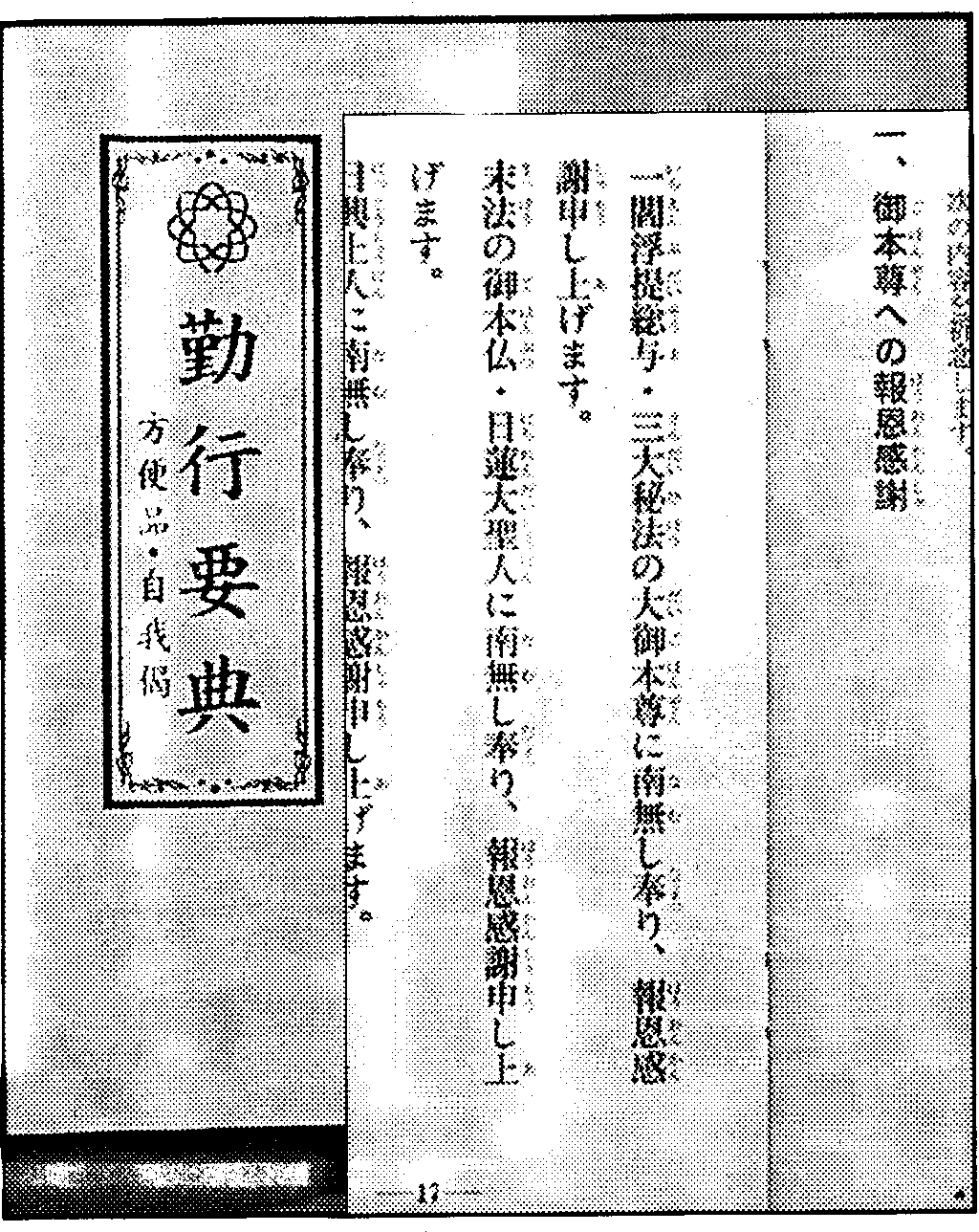
▲学会版勤行要典。いったい、「一閻浮提総与」の意味がわかった上で作ったのか、と、首を傾げたくなる