「通諜」の筆跡
A:学会が出してきた「通諜」のコピー=昭和52年頃出回ったという。昭和18年6月25日に戸田理事長名で発せられた通牒。神札を粗末に扱わないように指示されている。
B=学会が出してきた文書(ここでは「S文書」と呼ぶ)。作成者とされる法華講員S氏が、「通諜」も作成したという。
------------------------------------------------------------
A

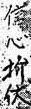
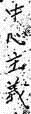
 B
B



 ←「心」/A「通諜」、B「S文書」
←「心」/A「通諜」、B「S文書」
▲「心」については、Aは小さい点(線)が2つとも短く、離れている。これに対してBは2つの点が長く曲がっている。さらに2つがつながっている(または、間隔が短い)。
A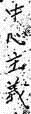 B
B ←「義」/A「通諜」、B「S文書」
←「義」/A「通諜」、B「S文書」
▲「義」については、Bの「 」はAに比べて水平に近く、しっかりはねている。全体的に言えることだが、「
」はAに比べて水平に近く、しっかりはねている。全体的に言えることだが、「 」について、Bはしっかりはねているのに対し、Aは、はねていない場合が多い。
」について、Bはしっかりはねているのに対し、Aは、はねていない場合が多い。
A B
B ←「誠」/A「通諜」、B「S文書」
←「誠」/A「通諜」、B「S文書」
▲「誠」については、Bの「 」はAに比べて長く傾きが大きい。また、しっかりはねている。書き順最後の点(線)も、Aに比べてBは極端に長い。
」はAに比べて長く傾きが大きい。また、しっかりはねている。書き順最後の点(線)も、Aに比べてBは極端に長い。
A B
B ←「城外」/A「通諜」、B「S文書」
←「城外」/A「通諜」、B「S文書」
▲「外」については、Aは「ト」の横線が真っ直ぐ斜めに下がっているが、Bは曲線で右上がり。見た感じも全く異なる。「城」については、ABで「土」の形が異なる。また、Bの「 」はAに比べて長く、しっかりはねている。「
」はAに比べて長く、しっかりはねている。「 」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。全体的に、「
」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。全体的に、「 」については、Aははねない場合が多く、Bはほとんどはねている。この特徴は「感」「誠」「職」「義」「戦」において顕著であり、両者の癖の違いがはっきり出ている。
」については、Aははねない場合が多く、Bはほとんどはねている。この特徴は「感」「誠」「職」「義」「戦」において顕著であり、両者の癖の違いがはっきり出ている。
★「 」は、本来はねる文字である。それを、一方でははねる場合が圧倒的に多く、他方では極めて少ない。本来はねる文字であるから、"正式な文書では丁寧に書いたためにはねて、私的なメモでは簡略化してはねなかった"ということであれば、考えられないこともない。しかし、この場合は逆である。組織内部への伝達用とはいえ、多くの人の目に触れる重要な文書の文字ははねていないのに、私的なメモ(Bはどうみてもメモ書き)の文字はしっかりはねている。これは一体どういう訳か?考えられる答えは"AとBは別人が書いたもので、Aの文書にはねない文字が多いのは、筆者本来の癖による"ということである。
」は、本来はねる文字である。それを、一方でははねる場合が圧倒的に多く、他方では極めて少ない。本来はねる文字であるから、"正式な文書では丁寧に書いたためにはねて、私的なメモでは簡略化してはねなかった"ということであれば、考えられないこともない。しかし、この場合は逆である。組織内部への伝達用とはいえ、多くの人の目に触れる重要な文書の文字ははねていないのに、私的なメモ(Bはどうみてもメモ書き)の文字はしっかりはねている。これは一体どういう訳か?考えられる答えは"AとBは別人が書いたもので、Aの文書にはねない文字が多いのは、筆者本来の癖による"ということである。
A B
B ←「戦」/A「通諜」、B「S文書」
←「戦」/A「通諜」、B「S文書」
▲Bの「 」はAに比べて長く、しっかりはねている。
」はAに比べて長く、しっかりはねている。
A B
B ←「感情」/A「通諜」、B「S文書」
←「感情」/A「通諜」、B「S文書」
▲AとBでは、「情」の書体が全く異なる。「感」については、Bの「 」はAに比べて長く、しっかりはねている。「
」はAに比べて長く、しっかりはねている。「 」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。
」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。
A B
B ←「職域」/A「通諜」、B「S文書」
←「職域」/A「通諜」、B「S文書」
▲AとBでは、何故か「職」の字体が異なる。
A
 B
B
 ←「てへん」/A「通諜」、B「S文書」
←「てへん」/A「通諜」、B「S文書」
▲Aの「折」「扱」ともにはねていない。Bは"てへん"だけでなく「斤」もはねている。Bの場合、他の文字の"てへん"もはねていると思われるが、画質が悪く、不明。
A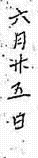 B
B ←「月日」/A「通諜」、B「S文書」
←「月日」/A「通諜」、B「S文書」
▲Bは全体に右に傾いている。またBは「月」が極端に細い。
A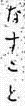
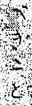 B
B
 ←「と」/A「通諜」、B「S文書」
←「と」/A「通諜」、B「S文書」
▲Aは「と」の縦線が短いが、Bは目立って長い。またA「と」の第2画はまるみを帯びているのに対して、Bのそれはとがった感じ。
A B
B ←「外」/A「通諜」、B「S文書」
←「外」/A「通諜」、B「S文書」
▲Aは「ト」の横線が真っ直ぐ斜めに下がっているが、Bは曲線で右上がり。見た感じも全く異なる。
A B
B ←「殿」/A「通諜」、B「S文書」
←「殿」/A「通諜」、B「S文書」
▲Aは左半分が「殳」に比べて極端に小さいが、Bは左右ほぼ同じ大きさ。また左に延びる線の長さもAは短く、Bは長い。


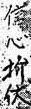
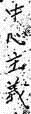
 B
B



 ←「心」/A「通諜」、B「S文書」
←「心」/A「通諜」、B「S文書」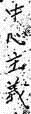 B
B ←「義」/A「通諜」、B「S文書」
←「義」/A「通諜」、B「S文書」 」はAに比べて水平に近く、しっかりはねている。全体的に言えることだが、「
」はAに比べて水平に近く、しっかりはねている。全体的に言えることだが、「 」について、Bはしっかりはねているのに対し、Aは、はねていない場合が多い。
」について、Bはしっかりはねているのに対し、Aは、はねていない場合が多い。 B
B ←「誠」/A「通諜」、B「S文書」
←「誠」/A「通諜」、B「S文書」 」はAに比べて長く傾きが大きい。また、しっかりはねている。書き順最後の点(線)も、Aに比べてBは極端に長い。
」はAに比べて長く傾きが大きい。また、しっかりはねている。書き順最後の点(線)も、Aに比べてBは極端に長い。 B
B ←「城外」/A「通諜」、B「S文書」
←「城外」/A「通諜」、B「S文書」 」はAに比べて長く、しっかりはねている。「
」はAに比べて長く、しっかりはねている。「 」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。全体的に、「
」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。全体的に、「 」については、Aははねない場合が多く、Bはほとんどはねている。この特徴は「感」「誠」「職」「義」「戦」において顕著であり、両者の癖の違いがはっきり出ている。
」については、Aははねない場合が多く、Bはほとんどはねている。この特徴は「感」「誠」「職」「義」「戦」において顕著であり、両者の癖の違いがはっきり出ている。 」は、本来はねる文字である。それを、一方でははねる場合が圧倒的に多く、他方では極めて少ない。本来はねる文字であるから、"正式な文書では丁寧に書いたためにはねて、私的なメモでは簡略化してはねなかった"ということであれば、考えられないこともない。しかし、この場合は逆である。組織内部への伝達用とはいえ、多くの人の目に触れる重要な文書の文字ははねていないのに、私的なメモ(Bはどうみてもメモ書き)の文字はしっかりはねている。これは一体どういう訳か?考えられる答えは"AとBは別人が書いたもので、Aの文書にはねない文字が多いのは、筆者本来の癖による"ということである。
」は、本来はねる文字である。それを、一方でははねる場合が圧倒的に多く、他方では極めて少ない。本来はねる文字であるから、"正式な文書では丁寧に書いたためにはねて、私的なメモでは簡略化してはねなかった"ということであれば、考えられないこともない。しかし、この場合は逆である。組織内部への伝達用とはいえ、多くの人の目に触れる重要な文書の文字ははねていないのに、私的なメモ(Bはどうみてもメモ書き)の文字はしっかりはねている。これは一体どういう訳か?考えられる答えは"AとBは別人が書いたもので、Aの文書にはねない文字が多いのは、筆者本来の癖による"ということである。
 B
B ←「戦」/A「通諜」、B「S文書」
←「戦」/A「通諜」、B「S文書」 」はAに比べて長く、しっかりはねている。
」はAに比べて長く、しっかりはねている。 B
B ←「感情」/A「通諜」、B「S文書」
←「感情」/A「通諜」、B「S文書」 」はAに比べて長く、しっかりはねている。「
」はAに比べて長く、しっかりはねている。「 」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。
」に交叉する線もAに比べてBは極端に長い。 B
B ←「職域」/A「通諜」、B「S文書」
←「職域」/A「通諜」、B「S文書」
 B
B
 ←「てへん」/A「通諜」、B「S文書」
←「てへん」/A「通諜」、B「S文書」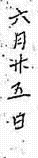 B
B ←「月日」/A「通諜」、B「S文書」
←「月日」/A「通諜」、B「S文書」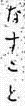
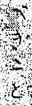 B
B
 ←「と」/A「通諜」、B「S文書」
←「と」/A「通諜」、B「S文書」 B
B ←「外」/A「通諜」、B「S文書」
←「外」/A「通諜」、B「S文書」 B
B ←「殿」/A「通諜」、B「S文書」
←「殿」/A「通諜」、B「S文書」