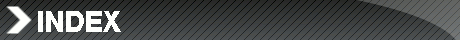(『要法寺日辰と同日舒の「一笑云云」について』高橋信興『大日蓮』H21.11抜粋編集)
●一、瀬兵衛跡目に吉右ヱ門才覚を以て武兵衛入候、是は時宗にて之れ有り候所に折々藤蔵に対して、法花経の有り難き事を承り、本法寺(福島市、要山末-筆者注)当住阿闍梨日賢のすゝめを請け内心は法花信心にて居り候なり。此の左京阿闍梨前寂日坊日賢と申すは、駿州富士大石寺より一宗の法式、並びに改宗のもの等不埒(ふらち)に付き、本法寺暫住に遣わさるるなり。尤も大石寺は当門流の大本寺なり(「改宗始終之記録」元禄年中、高橋藤蔵盛重等/『諸記録』能勢順道師編著16-320頁)
-----------------------
これによると、改宗した(福島市に富士門流大石寺の寺院がなかったために、要山末の本法寺へ改宗、あるいは大石寺末はなかったが、大石寺も要山も当時は大本寺と本寺の関係であったので一味同心の上から)人達がまだ初心なので、前寂日坊住職の左京阿闍梨日賢師が大石寺より遣わされて、富士大石寺の化儀・化法を教えられた。その改宗した人達はもちろん、当時の要山末僧俗は「尤も大石寺は当門流の大本寺なり」と称しております。
左京阿闍梨日賢師は本法寺に3ヵ年間、信徒を教化して、富士大石寺へ帰られました。その後、京都要法寺隠居の日舒が下着、本法寺が無住だったので、しばらく檀家の願ひにより住職になった(『諸記録』16-329頁)と記されておりますように、初めは初心の人達に、前述のとおり、富士門流大石寺の化儀・化法をもって大石寺より前寂日坊日賢師が赴任教化され、その後、京要法寺門流から日舒が住職をしています。これは、述べるまでもなく、大石寺を大本山と仰ぎ、要法寺を本山と見て、なんの抵抗もなく信仰していた証左でありましょう。
●一、日永上人、元禄十三年五月七日、加藤左五兵衛尉授与。
一、日宥上人、宝永五年二月十一日、鎮護、加藤左五兵衛尉授与。
一、日寛上人、享保五年正月十五日、加藤庄之助授与。
一、日詳上人、享保十七年正月二十三日、加藤庄兵衛授与(抄録)
『諸記録』(16-447頁~449頁)
-----------------------
要山末、福島・立子山一円寺の檀家である加藤家へ授与された御本尊。御本尊も大石寺へ願って、時の法主上人より下付いただいていた。
●宗祖御筆御本尊、御真蹟断簡二行、興師御筆(御形木歟)、時師御筆、主師御筆、昌師御筆の御本尊(抄録)
-----------------------
が自宅の御宝蔵に格護されています。この加藤家は要山日舒の生家であると言われていますが、一考を要すると思われます。
●富士大石寺卅一代日因上人御筆
本堂御棟札 松尾山一円寺 廿九代
随喜阿本善院日仁判
宝暦九辰 巳午(卯カ) 年(春?)
(『御開山日尊上人第六百五十遠忌記念一円寺』誌に写真掲載)
●㊨棟札一円寺 本堂客殿造立之 宝暦十一 辛巳 正月大吉祥日三十一代日因花押
七十五歳
㊧授与之 大日本国奥州伊達郡立子山一円寺
當(住?)本善坊日仁比丘
(同上)
-----------------------
上記加藤家の檀那寺である要山末・一円寺についての記録。日因上人御筆の棟札の写真が掲載されています。本善院(坊)日仁師は、かつて大石寺百貫坊の歴代であり、一円寺に25年住して同寺を復興され、「中興の師」と仰がれています(同上)。大石寺と要山末の一円寺の当時の縁浅からぬ関係を示しています。
●(前略)明和五 太才戊子 稔九月吉祥日 富士大石師(寺カ)
駿河阿闍梨日堅之を誌す。
南無妙法蓮華経 松尾山一円寺
大願主(当山廿九世)随喜阿闍梨日仁在リ判(以下略)
(『松尾山一円寺縁起』/堀日亨上人ノート)
-----------------------
日因上人より棟札を授与されてより、7年ほど経過して、さらに梵鐘を鋳造した折、その鐘銘を当時、大石寺学頭の日堅師(のちの大石寺第36世法主)よりいただいています。『松尾山一円寺縁起』に、「●」とあります。
以上、述べてきたように、要法寺の末寺であり、またその檀家でありながら、大石寺の歴代上人等より、棟札や鐘銘をいただき、御本尊が授与されているということは、その当時は再三述べてきた如く、要山門流も大石寺を大本山と仰いで信仰されていたが故であります。
現在、要法寺の末寺の福島・立子山の一円寺、同渡利の仏眼寺等の檀家となっている家のなかには、大石寺歴代上人から御本尊を授与されている家もあるそうです(今後さらに詳細に調べる必要がありましよう)。
往時の富士大石寺中心の信仰の姿が偲ばれます。(中略)
しかし、これより以後には(江戸末期から明治初期)、要山門流においては大石寺と同じ信仰の心を持つ人々と、全く反対(もちろん中間の人々もいたはず)の人々と、波をうねらせながら時代を過ごしてきました。現在では大石寺への反抗派が要山教団の表面を覆っているようです。
1日も早く昔日の大石寺総大本寺との晴れやかな信心に戻ってほしいと念うものです。
かつて、4百年ほど前、要山第18代日陽が(元和3年4月14日)、
●爾来駿州富士大石寺は興師御開闢の地なり門徒の本寺たるに依って此の地に詣でんと志し(中略)御霊宝等残らず頂拝す、中にも日本第一の板御本尊(中略)拝覧し奉る(『富要』第5巻59頁)
と述べて、門徒の本寺たる大石寺に詣でた(拝覧)と言われたように、これから要山門流の僧俗には、かつての正行に思いを馳せて帰仰されんことを希(ねが)うものです。