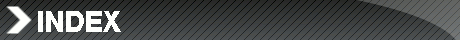もし自由民主党が過半数の議席を失なうというようなことになった場合、公明党に手をさしのべてこれとの連立によって圧倒的多数の政権を構成するならば、そのときは、日本の保守独裁体制が明らかにファシズムへのワンステップを踏み出すときではないかと思う。
(公明党が)自民党と連立政権を組んだとき、ちょうどナチス・ヒトラーが出た時の形と非常によく似て、自民党という政党の中にある右翼ファシズム的要素、公明党の中における宗教的ファナティックな要素、この両者の間に奇妙な癒着関係ができ、保守独裁体制を安定化する機能を果たしながら、同時にこれを強力にファッショ的傾向にもっていく起爆剤的役割として働く可能性も非常に多くもっている」
この本はいまも「生きている」と思うが、残念ながら文庫化等はされていない。
------------------------------------------------------------
※●区社会教育部長に対してこう質問したのは公明党所属の田口仁氏だ(当然、創価学会員である)。 筆者は本人を直撃したことがあるが、同氏は図書館からこれらの出版物を排除する理由すらまともに答えられなかった。また、同様の質問は他の議会でも公明党議員によって行われていた。(山田直樹『週刊新潮』H15.11.6)



『中外日報』
―今、新たに振り返る「あの頃のこと」―
―たまたま眼にした小さな訃報―
(元創価学会顧問弁護士・山崎正友『慧妙』H20.2.1)
【たまたま眼にした小さな訃報】
昨年秋、創価学会との訴訟準備のため、図書館に出かけた折、たまたま眼にした10月18日付『中外日報』に、次のような、小さな訃報(ふほう)記事があるのを見つけました。
「本間昭之助氏、死去。中外日報の元社長で(財)京都仏眼協会前理事長の、本間昭之助氏が8月下旬に死去していたことが、このほど分かった。78才だった。関係者によると、3年ほど前に脳梗塞(のうこうそく)で倒れて以来、療養生活を続けていたが、詳細は近親者・関係者以外には知らされていなかった。山形県生まれ。中外日報社の東京支社長を経て、昭和50年4月に代表取締役社長に就任。平成9年12月に解任されるまで22年間、社長を務めた。」
22年間も社長を務めた人物の訃報を報じるにしては、いかにもよそよそしく素っ気ない扱いであり、そもそも、「8月下旬に死去していたことが、このほど分かった」と、死後2ヵ月も経(た)って、死去の日付すら曖昧(あいまい)な記事を掲載した、というところに、社長を解任されてからの本間氏と「中外日報社」との関係が窺(うかが)われます。
【学会の手先を務めた『中外日報』】
読者の方々の中には、平成3年の創価学会破門に際しての、『中外日報』紙による激しい宗門攻撃、そして、その後も平成9年まで続いた、毎号1面を丸々使っての宗門攻撃、創価学会批判を行なうマスコミやジャーナリスト、あるいは脱会者や反学会勢力に対する、えげつないスキャンダル攻撃を、覚えている方もおられるでしょう。
かくいう私も、創価学会が謀略によって作り出したスキャンダルをもとに、連日のように『中外日報』に攻撃されました。
とくに、平成8年に行なわれた総選挙において、「民主政治を考える会」の"緊急レポート"ビラ5千万枚の配布によって新進党が敗北し(創価学会、元新進党関係者はそう言っています)、それが引き金となって新進党が分裂する、という騒ぎの後は、私は、『中外日報』の最大のターゲットとされました。
このビラの仕掛け人が私であり、「代表世話人の内藤圀夫は、ただ名前を貸しただけで、実際は、山崎が一切を取り仕切ってやったことだ」と思い込んだ創価学会は、私を、日蓮正宗・御法主上人に次ぐ仇敵(きゅうてき)としたのです。そして、創価学会の意を受けた『中外日報』が、怪文書や、私に対し訴訟を起こした女性の「上申書」等を材料に、紙面で攻撃し、そして、これを創価学会が、『聖教新聞』『第三文明』等で「一般紙によれば……」という形で取り上げる、というデッチアゲの方程式が確立しました。
【学会の『中外日報』浸食の"手口"】
そもそも『中外日報』は、真渓涙骨氏が明治30年に『教学報知』の名前で創刊した仏教新聞であり、『中外日報』と改題してからは、我が国唯一といってよい総合的な仏教紙として、存在していました。
その昔は、司馬遼太郎氏が大阪の新聞記者時代に『中外日報』紙に連載した「梟(ふくろう)の城」で、直木賞を受賞するなど、由緒と権威のある仏教紙でした。
戦後、創価学会が出現してからは、仏教界を背景とする新聞として、創価学会に対し批判的な立場を取ってきましたが、昭和49年頃から、『中外日報』の論調が様(さま)変わりしはじめました。次第に、反創価学会色が薄れ、やがて、さりげなく創価の提灯記事が掲載されるようになりました。
じつは、この頃、東京支社長であった本間氏が、経営不振の打開策として、創価学会にすり寄ったのです。
その前から本間氏は、『中外日報』を背景に、各教団の紛争に介入しては、金を出す方に味方し、出さない方を叩くという、いわゆる「宗教ゴロ」に手を染めるようになり、そのことも部数を減らす原因となっていましたが、本間氏の主導で、創価学会をスポンサーとして、経営立て直しを図ったのでした。
この頃、本間氏は、創価学会に入会しています(立場上、秘密にしていましたが、当時、大石寺境内で見かけた人もあります)。
読者の方の中には、昭和50年頃、『中外日報』が、日蓮正宗寺院や有力な幹部に、無料で送られていたことを覚えておられる方も、いらっしやると思います。
学会は、「マスコミを味方に付けるため」「宗内に、他宗の状況を知ってもらうため」等と説明していたようですが、とにかく、無料で多くの寺院や幹部に配られ、そしてその代金は、創価学会が一括して支払っていました。年間2千万円くらいだったでしょうか。
ちょうどこの頃、私は創価学会において、「情報謀略師団」を指揮し、敵対勢力に対する攻撃や、情報収集を行なっていました。
昭和48年頃、当時の創価学会にとって最大の敵であった「新宗連」(新宗教団体連合会)、その主力教団である立正佼成会・PL教団に対する攻撃のため(池田大作は、「言論問題」の時、「新宗連」に非難されたことを根に持っており、その仕返しの意味もあって、私に、攻撃を命じたのです)、当時、「新宗連」理事長が管理していた「社団法人日本宗教放送協会」という休眠中の公益法人に目を付け、これを、元「新宗連」関係者をダミーとして、5百万円で買収しました。
そこへ当時、私の配下であった北林芳典(現・報恩社〈葬儀会社〉社長。怪文書『地涌』の関係者)を、「大山正」という偽名で派遣し、これを編集長にして『宗教評論』という機関紙を発行させ、「新宗連」や立正佼成会、PL教団等に対する、陰険で下劣な攻撃をやらせました。「新宗連」関係の法人が、突然「新宗連」等を攻撃したものですから、相手は面食らいました。
北林は、この時、『中外日報』の本間氏と親しくなり、その、「宗教ゴロ」の片棒を担(かつ)ぐようになりました。北林は、私にこれを、「カムフラージュのため」と言って誤魔化していました。
そのうち、昭和55年になって、私や原島嵩氏が学会に造反し、内部告発を開始すると、北林は、私に対する攻撃の急先鋒となりました。そして、『中外日報』も、創価学会擁護(ようご)の論陣を張りました。
平成3年、日蓮正宗が創価学会を破門すると、『中外日報』は、マスコミの中で唯一、創価学会の肩を持って、宗門攻撃を行ないました。そして、さらに、私や乙骨正生氏、段勲氏、内藤圀夫氏、「四月会」や、自民党の創価学会批判に対し、攻撃を行なったのです。
その記事は明らかに、創価学会の入れ知恵か、あるいは、創価学会のゴーストライターが書いたと見られるものもありました。
創価学会の危急存亡にあたって、本間氏は、『中外日報』の、仏教紙として一般仏教界を基盤としてきた立場をかなぐり捨てて、『聖教新聞』以上に、創価学会の敵対者に攻撃を加え続けました。
仏教界も世間の識者も眉(まゆ)をひそめ、社内からも強い反発がありましたが、創価学会からの支援をバックに、ワンマン体制を敷いていた本間氏は、こうした批判に耳を貸そうともしませんでした。
【更生の端緒は『自由の砦』の特報】
ところが、平成8年9月8日付『自由の砦』(創価学会による被害者の会機関紙)で、中外日報社から流出した内部資料に基づき、創価学会が年間8千5百万円もの大金を中外日報社に提供して丸抱えし、創価学会の代弁をさせている事実を暴露(ばくろ)しました。このことが引き金となって、他の仏教教団が『中外日報』の購読を打ち切るようになり、そのため、いよいよ『中外日報』は経営不振に陥(おちい)りました。
そうした状況の中、中外日報社で、本間氏に対するクーデターが勃発(ぼっぱつ)したのです。
株主や社員、有力関係者が密(ひそ)かに協議を重ね、その結果、平成9年12月24日に開かれた取締役会で、本間昭之助氏は突然、社長を解任されました。
そして、平成10年3月3日付1面に、「中外日報が変わります」「『不偏不党』の立場を貫く」「真実で公正な報道・論評へ」「恣意(しい)的な紙面作り打ち切り『刷新』」等の大きな見出しで社告を掲載し、
「近年、不幸にして、創刊者涙骨翁の精神に背(そむ)き、『公器』である紙面の一部が歪められてまいりました。(中略)私どもは、昨年12月24日、恣意的な紙面作りを断ち切るために、前社長を解任しました。独立不羈(ふき)の記者魂で蹶(けっき)した私どもの微衷(びちゅう)をお酌み取りいただければ幸いです。この上は、創刊の精神にかえって、『紙面刷新』に取り組みます。(中略)我が真渓涙骨社主の命日である4月14日を起点に、紙面を刷新します」
と宣言したのです。
これ以後、『中外日報』の、創価学会ベッタリの記事は姿を消しました。
創価学会の金に目がくらみ、公器である新聞の紙面を歪めた本間氏は、それっきり、表舞台から姿を消し、消息も聞かれませんでした。
『中外日報』も、完全に本間氏との関係を断った、ということでした。
今回の訃報により、本間氏は3年もの間、不自由な生活をした末、昨年8月に息を引き取ったことが明らかとなりました。そのことを、『中外日報』ですら10月下旬まで知らなかったのです。
こうして、社長を追放してまで創価学会との関係を断ち切った『中外日報』は、宗教紙としての姿を取り戻しましたが、創価学会に骨の髄(ずい〉まで虜(とりこ)になった本間氏の人生の寂しい終焉(しゅうえん)は、いろいろ考えさせられるところがあります。氏の冥福(めいふく)を祈ります。
私は、創価学会との間で多数の訴訟を抱え、しばらく身動きできない状態にありましたが、これを契機に、再び「あの頃のこと」を再開し、今後は、創価学会の極秘内部資料に基づいて、自らの「本仏化」と「創価学会の私物化」「日蓮正宗支配の野望」そして「それが叶(かな)わぬ時は、在家教団としての独立を目指す」という、宗・創間の紛争の原因となった池田大作の本音を明らかにしていくつもりです。
さらに、できれば、昭和55年以後の「正信会との関わり」と紛争の真実を、明かしていきたいと思っています。
[画像]:学会の呪縛が解けた『中外日報』(H10.3.3)=「恣意的な紙面作り断ち切り刷新」の文字が
------------------------------------------------------------
◎明治30年 真渓涙骨氏が仏教新聞『教学報知』を創刊。『中外日報』と改題してからは、我が国唯一といってよい総合的な仏教紙として存在
◎ 戦後、創価学会が出現してからは、仏教界を背景とする新聞として、創価学会に対し批判的な立場を取ってきた
◎昭和49年頃
・東京支社長であった本間氏が、経営不振の打開策として、創価学会にすり寄る。
・『中外日報』の論調に反創価学会色が薄れ、やがて、さりげなく創価の提灯記事が掲載されるようになる
・本間氏、創価学会に入会
◎昭和50年4月 本間氏、代表取締役社長に就任
◎平成3~ 創価学会破門に際しての、『中外日報』紙による激しい宗門攻撃、そして、その後も平成9年まで続いた、毎号1面を丸々使っての宗門攻撃、創価学会批判を行なうマスコミやジャーナリスト、あるいは脱会者や反学会勢力に対する、えげつないスキャンダル攻撃。これを創価学会が、『聖教新聞』『第三文明』等で「一般紙によれば……」という形で取り上げる、というデッチアゲの方程式が確立
◎平成8年9月8日 『自由の砦』(創価学会による被害者の会機関紙)で、中外日報社から流出した内部資料に基づき、創価学会が年間8千5百万円もの大金を中外日報社に提供して丸抱えし、創価学会の代弁をさせている事実を暴露(ばくろ)。このことが引き金となって、他の仏教教団が『中外日報』の購読を打ち切るようになり、そのため、いよいよ『中外日報』は経営不振に陥(おちい)る
◎平成9年12月4日 取締役会で、本間氏が突然、社長を解任される。株主や社員、有力関係者が密(ひそ)かに協議を重ねた結果の「クーデター」
◎平成10年3月3日 『中外日報』1面に、「中外日報が変わります」「『不偏不党』の立場を貫く」「真実で公正な報道・論評へ」「恣意(しい)的な紙面作り打ち切り『刷新』」等の大きな見出しで社告を掲載
●近年、不幸にして、創刊者涙骨翁の精神に背(そむ)き、「公器」である紙面の一部が歪められてまいりました。(中略)私どもは、昨年12月24日、恣意的な紙面作りを断ち切るために、前社長を解任しました。独立不羈(ふき)の記者魂で蹶(けっき)した私どもの微衷(びちゅう)をお酌み取りいただければ幸いです。この上は、創刊の精神にかえって、「紙面刷新」に取り組みます。(中略)我が真渓涙骨社主の命日である4月14日を起点に、紙面を刷新します(『中外日報』H10.3.3)
◎平成19年8月下旬 中外日報の元社長で(財)京都仏眼協会前理事長の本間昭之助氏が死去
◎平成19年10月18日 『中外日報』、本間氏の訃報掲載



『中外日報』は一時期、学会の資金が流入するとともに、学会が同新聞を大量に買い付けていたという事実が、宗門側の新聞によって暴露されたことがあります。このような背景事情があって『中外日報』は、「学会の御用新聞」のごとき報道を繰り返し行ったのです。
つまり、学会の御用新聞が、学会に加担した報道を流していただけのことであり、何の信憑性もないことは明らかです。
そして内外から、その偏った報道姿勢に非難を浴びました。そのため同新聞は、平成10年に、第1面全体を割いて、それまでの学会偏向の報道姿勢を反省し、改める旨を表明しています。↓
[画像]:偏向報道を謝罪する『中外日報』



(『慧妙』H8.9.16編集)
<一般紙も「金のために身を売った」と批判>
●『中外日報』という仏教業界紙がある。明治に始まり、近く創刊百年を迎えようという、由緒のある隔日刊紙である。
ところがこの新聞、2、3年前からおかしくなっている。創価学会の提灯持ち記事がやたらと多くなったのだ。
おかしくなったのは、創価学会が日蓮正宗と対立してからである。正宗の僧侶を悪し様にこきおろす記事が目立つようになった。親しい記者に尋ねると、実は社長が、資金難を逃れるために学会の金に取り込まれてしまったのだという。
記者の中にも、こんなことではいかんと考えている者もいないわけではないが、社長は聞く耳を持たないのだという。(中略)
最近は『聖教新聞』の転載がよく出るが、8月22日には、『週刊新潮』の批判本を出した著者にインタビューした大きな記事が出ている。
なぜ『週刊新潮』の内幕を問題にするのかと言えば、創価学会批判の記事をよく載せるからである。
この批判者(※批判本の著者)によればバックナンバーをすべて取り寄せて「目次を研究」した。その結果、「最初は格調が高かったのですが、だんだん、どうも下半身の問題であるとか、創価学会、あるいは共産党とかいったものを叩くことを方針としているような感じ」が出て来たという。ここで「下半身の問題」を言うのは、近く裁判の始まる、池田大作のレイプ事件を念頭に置いている。
しかし、これは語るに落ちた話で、『中外日報』の記事がおかしいと私が気づいた最初は、連日、正宗僧侶や夫人の「下半身記事」を、これでもかこれでもかと掲載し続けたからである。
マスコミをスーパーとすれば、このような新聞は専門店。個性的で気骨のある専門店メディアの健闘を心から期待する者の1人として、金のために良心を売った「宗教」新聞の存在は、まことにうら寂しい事件ではある。(平成8年9月1日付『産経新聞』コラム・斜断機)
<発行部数の約半分を学会が購入>
一般紙もこれほどの関心を寄せる、創価学会と『中外日報』のただならぬ関係-今般、それを裏付ける内部資料が流出し、本紙もそのコピーを入手した。それは、「注文請書」と印刷された1枚の伝票であった(別掲)。
御覧のように、この伝票は、『中外日報』2400部の1ヵ月あたりの定期購読代金696万円を、月末で締め、翌月末に指定口座に振り込む-という内容。
受注者の欄には「株式会社中外日報東京本社」のゴム印と角印、発注先欄には、印刷文字で「創価学会」と。
書式からいって、伝票そのものは創価学会の専用用紙らしいが、その右肩に「轟局長様」とのメモ書きがあるように、この伝票、中外日報東京本社から京都本社の轟局長宛てに送られたものだという。中外日報東京本社は、創価学会からの受注状況を京都本社へ報告するにあたって、創価学会への「注文請書」の写しを、そのまま送ったということか。
しかも一説によれば、『中外日報』の発行部数は5000部程度だという。つまり創価学会は『中外日報』の発行部数の2分の1近くを買い取ってしまっていることになる。
これによって、創価学会が年間に中外日報社に支払っている購読料は、8352万円にのぼる。
しかも、学会から同社に流れる金は、こうした正規の購読料ばかりではない。聖教新聞社や第三文明社が、『中外日報』に、ほぼ定期的に3段ぶち抜き広告などを掲載しているのだから、その広告料も、莫大な額にのぼるはずだ。
<狡猾な『中外日報』利用法>
平成3年3月4日発行の『微笑』に、日顕上人猊下のゴシップ記事が載った。
”猊下に隠し子が?”と思わせるような見出しの付いたその記事は、女性週刊誌によくありがちな、冗談話をおもしろおかしく脚色しただけの記事であった。
すなわち、猊下と幼なじみだ、という女性が、猊下に対する淡い初恋の思い出なるものを週刊誌記者に語っただけの、じつにたわいもない記事だったのであるが、インタビューの中で、その女性の次女について、”猊下との不義の子であり、妊娠中も土手から飛び降りるなどして流産しようとした”との噂があるが、と記者が問い掛けたのに対し、その女性は、”次女も間違いなく夫の子供”と断言。さらに、
「私、冗談好きだから。それが結果的に、みんなにウソをつくことになったかも知れませんね。血液型を調べれば分かりますよ」と、重ねて全面否定した。
ところが、この記事に基き、後日、『中外日報』(平成3年11月19日・20日号)は次のように報じた。
「この女性は、人妻となったにもかかわらず、信雄(※しんのう・日顕上人御登座前の御名)さんと”焼けぼっくいに火”がついて妊娠し、土手から飛び降りるなどして流産をしようとしている。罪な話である。この”妊娠事件”が本山内で噂となったのであろう。日顕氏の輝ける経歴の中でこのことが紛れのない汚点として残っている。」
「マスコミ紙上(※『微笑』のこと)を賑わしたのが、日顕法主に隠し子がいたという事実。『信雄さんは初恋の人』と法主の幼名で懐かしそうに思い出を語る女性が登場。その告白が真実とすれば、日顕猊下と彼女の間に産まれた子供は、娘さんで現在44歳という。」
こうして、『微笑』に掲載されたたわいもない記事は、『中外日報』の手によって、正反対の趣旨へとネジ曲げられ、無惨な女性スキャンダルに捏造されてしまったのだ。
しかも、この捏造スキャンダルが、さらに脚色され、他のデッチ上げ話も付け加えられて『創価新報』(平成3年12月4日号)紙上に「宗風を汚した日顕法主の暴力と遊蕩・法滅の家系、3代にわたる”かましの血脈”」との、おぞましい見出しの付いた誹謗記事となっていったのだから、呆れて物が言えない。
これが、創価学会による『中外日報』の代表的な活用法の1つである。
これ以外にも創価学会は、一般人がほとんど目にすることがない『地涌』その他の怪文書を、まず『中外日報』紙上に取り上げさせ、さらに、その『中外日報』の記事をネタに、今度は「あるマスコミの報ずるところによれば・・・」等々といって、『創価新報』や『聖教新聞』で大々的なキャンペーンを繰り広げてきた。
つまり、自ら捏造したスキャンダルを、『中外日報』というメディアに取上げさせることで、それがあたかも巷間に報じられた周知の事実であるかのように見せかけ、末端会員や、学会御用達の一部の学者やジャーナリスト達を洗脳し続けてきたのである。
そのウラには、いざとなったら責任の全てを『中外日報』に負わせて”とかげの尻尾きり”をしよう、という薄汚いハラがあることは間違いない。
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
◆昭和17年8月12日付けの宗教新聞『中外日報』の記事である。見出しは、大きな活字で、こう出ていた。
「神本仏迹か、仏本神迹かの教義信条問題を公開せん
日蓮正宗の維新断行に護国憂宗の士ら遂に起つ」
笠原の策謀が、このような記事にデッチあげられたのだ。(『人間革命』第6巻82頁)
◆そのとき、森川一正が、笠原の策謀になる『中外日報』の10年前の記事を、ある学会員の先輩のところから入手して、持参したのである。700年祭を前にして、かつての笠原の活動が、いかに悪辣であったかを、この記事は、決定的に証拠づけていたといってよい。笠原を宣揚する記事が、はからずも笠原の罪状を、そのまま語ってしまっている。(『人間革命』第6巻85頁)
-----------------------
戦時中の『中外日報』は、獅子身中の虫たる宗内僧侶の側に立って「デッチあげ」の記事を掲載していた。そのような新聞に信を置いて、今度は学会自身が宗門誹謗のために「デッチあげ」の記事を利用したのである。



言論問題
(『フォーラム21』ほか)
[画像]:創価学会による言論出版妨害事件が世に知れ渡るきっかけとなった、藤原弘達著『創価学会を斬る』(『慧妙』H20.4.1)
<S44.8末>
・藤原弘達氏(※明治大学法学部教授)が「この日本をどうする」という警世キャンペーンシリーズの第1巻として、『日本教育改造法案』を出版。その車内吊り広告の脇に、次回作『創価学会を斬(き)る』の出版を予告。(『慧妙』H15.7.16)
・これに対して創価学会・公明党は、池田大作会長(当時)の指示のもと、『創価学会を斬る』の出版妨害に着手。
<出版妨害>
●(※昭和)44年8月末、朝早く北条さんから自宅へ電話をもらい、私は学会本部で池田から1つの仕事を命じられた。(中略)(北条・秋谷同席で、池田大作は)「政治評論家の藤原弘達が学会批判の本を出そうとしている。選挙前にこんな本が出るのは邪魔だ」「藤原君は、彼と面識があっただろう。すぐに相手と話をつけて、余計な雑音を押さえろ」池田はいつもこの調子だった(藤原行正=元創価学会渉外局長『池田大作の素顔』H1.4発行112頁/『フォーラム21』H15.7.1)
・S44.8.31 池田の命を受けた藤原行正氏は、、著者の藤原弘達氏宅を訪ねるも、交渉は不調に終わる。(『慧妙』H15.7.16)
・9.4 藤原行正氏は、出版社である日新報道に出版中止を掛け合うが、これも不調。(同上)
・9.14 今度は秋谷栄之助と藤原行正氏が藤原弘達氏と面談。1時間45分に及び交渉するが、やはり不調に終わる(この時の会談の内容は藤原弘達氏によって録音され、後に公表されることとなる)。(同上)
●創価学会批判の本が出るというので、私が田中さんに頼んで仲介に動いてもらった(竹入義勝=元公明党委員長『朝日新聞』H10.8.26/『慧妙』H15.7.16)
・10.6 田中角栄はまず、藤原弘達氏に架電。(同上)
・10.15 田中角栄、赤坂の料亭に藤原弘達氏を呼び出し交渉。この時、隣の部屋で、交渉の行方に聞き耳を立てている池田大作と竹入氏の姿を、料亭の仲居が目撃。後に『サンケイ新聞』がその事実をスッパ抜く。(同上)
・10.23 田中角栄が再度、藤原弘達氏と面談するが、結局すべて不調に終わる。(同上)
●昭和44年から46年にかけて藤原弘達氏が創価学会批判を繰り返した時には、私と竹入とで田中氏に調停を頼みにいった。田中氏は「よっしゃ」と快く引き受け、赤坂の料亭に藤原氏を呼び、仲介の労をとった。結果は破談だった。我々は隣室に控えて待っていたのである。(矢野絢也=公明党元委員長『矢野回想録』29頁/『前衛』H15.7)
-----------------------
田中は赤坂の「愛用の料亭」・「千代新」に『創価学会を斬る』の著者・藤原弘達明治大学教授を呼びだし、「初版分は全部買い取ろう」と持ちかけた。しかし、藤原は出版の意思を変えなかった。このとき隣の部屋で、公明党の竹入委員長と矢野書記長が息を殺して事態の推移を見守っていたことを、藤原教授は気づいていたのだろうか。なお、田中が藤原に会ったのは「池田の依頼」であり、このときの「2人のやりとりを池田は仕切り越しにじっと聞いていた」(野田峯雄『池田大作金脈の研究』)という説もある。もし、それが本当なら、池田は竹入や矢野とは別に、田中・藤原会談の様子をうかがっていたということになる。(『前衛』H15.7)
●田中氏の仲介も不調に終わると、池田大作は潮出版社や聖教新聞社の社員を動員して書店を回らせ、『創価学会を斬る』を店頭に並べないよう、圧力をかけて回りました。(元創価学会顧問弁護士・山崎正友『慧妙』H20.4.1)
●私は、業務命令で書店に行かされました。
たしか全員で19名だったと思います。本が店頭に並ぶ少し前に、各部門から選抜されたメンバーが急遽、集められました。聖教新聞社の広告局、業務局(新聞販売部門)、出版局(書籍販売部門)、潮出版社からも来ていました。場所は聖教旧館の隣にあった業務局が入っていた建物の2階仏間で、私は出版局からの選抜です。責任者は出版総局長だった横松昭、出版局次長だった青柳清が現場の指揮をとっていました。
そこで聞かされたのは、こんな話です。「藤原弘達が『創価学会を斬る』という本を出す。創価学会を批判するとんでもない本だ。書店を回ってそれを押さえろ」。書店での口上も指示されました。「この本を、ここにある棚から中にしまってください。そうしてもらえなければ、『人間革命』などの扱いをしません」。『人間革命』は書店にとって売れ筋の本でしたから、十分圧力になると考えたのでしょう。そして最終的には、「創価学会を敵に回すのか」と。そこまで圧力をかけろといわれたんです。
青柳のもとで書店を地域別に分けて担当する区を決め、行動開始です。青柳が北條さん(浩・後に第4代会長、故人)から「お前が中心でやれ」と命令されたと聞きました。期間は1ヵ月前後だったと記憶しています。(岩崎文彦・昭和43年聖教新聞入社。聖教新聞社出版局、広告局、業務局等を経て、同55年退職。男子部総合ブロック長、壮年部では支部幹部等を務める。/『フォーラム21』H15.7.1)
・同時期、池田大作は、後にリクルート事件で有名になる池田克也(当時は潮出版社勤務)に命じ、大手書籍取次店や大手書店に圧力をかけさせる。(『慧妙』H15.7.16)
・創価学会に批判的な報道に抗議することを主たる任務とする全国各地の言論部員に、藤原弘達氏と日新報道に対して激しい抗議を行わせたため、藤原弘達氏の自宅や日新報道には、「ぶっ殺すぞ」とか「地獄に堕ちる」といった脅迫まがいの電話や手紙が、連日、殺到。抗議の葉書や手紙の量は段ボール箱数箱分にのぼるまでになった。
●それはひどいものでした。(※抗議の葉書、手紙が)やはり段ボール箱で何箱にものぼったんじゃないでしょうか。電話での脅迫もひどいものでしたので、警察がそれとなく藤原弘達氏のお子さんなど家族の警備をしたほどでした。ですから藤原弘達氏は身の安全を図るため、都内のホテルを転々として『創価学会を斬る』の執筆を続け、私たちも移動しながら編集作業を続ける有り様でした。なお、この抗議電話や葉書は出版後もますますエスカレートし、内容もひどいものでした。(遠藤留治=日新報道代表取締役『フォーラム21』H15.7.1)
<S44.11上旬>
・『この日本をどうする2 創価学会を斬る』(日新報道出版部刊)出版
第1部、実態―これが創価学会の正体だ
第2部、分析―その病理を衝く
第3部、展望―その危険なる未来
●日本の政党政治、民主主義の前途を考えた場合、なんらかの意味においてこの創価学会・公明党という存在に対する対決を回避しては、日本の議会政治、民主政治はとうてい健全に育たないという強い確信をもったからにほかならない(同書「まえがき」から)
・この本の「まえがき」で藤原氏は、出版にあたって創価学会・公明党から妨害を受けていたことを明らかにした。一部週刊誌も、この「まえがき」を取り上げた。(『前衛』H15.11)
<S44.12.13>
・NHKで放映した総選挙特集番組「2党間討論(公明党-共産党)」で、共産党の松本善明氏が、「創価学会を斬る等の出版物に、創価学会・公明党が出版に圧力、妨害をくわえている」と、発言。受けて、公明党の正木良明氏が、「そんなことはしていない。すべてウソである」と、反論。
<S44.12.17>
・これに怒った藤原氏は、『赤旗』で、田中角栄自民党幹事長が公明党の竹入委員長の依頼で、この本を世に出さないためにさまざまな働きかけをしていたことを暴露。創価学会が組織的に印刷、広告、取次店から小売店まで、圧力をかけたことも明らかになった。
<明らかにされた過去の「言論弾圧」>
・ロシア文学者の草鹿外吉氏ら5氏のよびかけで、12月23日に「言論・出版の自由にかんする懇談会」がひらかれた。この「懇談会」によって、いくつかの具体的事例が明らかになった。
―内藤国夫著『公明党の素顔』(エール出版社)の場合―
67年1月ごろから、三一書房からの執筆依頼で、都庁担当新聞記者として取材してきた都議会公明党の素顔を書きはじめたという。これが創価学会・公明党の知るところとなり、出版社に圧力がかかり、出版計画は中止となる。内藤氏は出版社を変更し、極秘裏に出版準備をつづけたが、印刷工程でゲラが創価学会にわたった(業務上横領の疑い)ようで、公明党の竹入委員長が30数箇所の書き換えや削除を要求してきた。さらに、国際勝共連合の背後にいた右翼の頭目の笹川良一が内藤氏に「わしは公明党に前に1度恩を受けている。本はおれが全部買いたい」といってきたことも明らかにされた。この本は69年5月に出版されたが、大手取次店は配本を拒否し、小売店に宣伝して注文をとるという方法で、わずかに世に出された。(『前衛』H15.11)
―元創価学会員・植村左内著『これが創価学会だ』の場合―
まだ本が出ないうちに、池田会長と竹入委員長が出版社を相手どり、図書発行等禁止仮処分申請をおこなった。東京地裁が、まだ本ができていないことを理由に申請を却下すると、今度は名誉毀損として告訴。この本も取次店が扱いを拒否した。68年12月には、出版社と創価学会・公明党の間に示談が成立し、出版社は著者に無断で印刷過程のすべてを創価学会・公明党にわたしてしまった。出版社への圧力には、福田赳夫、賀屋興宣という自民党中枢が関与し、宗教センター理事長で日本大学会頭の古田重二良氏が示談をまとめたという。庭野日敬立正佼成会会長(当時)によれば、古田氏は、立正佼成会に買い取られて配られた本を信者から取りもどし、日大校庭で焼いてしまったそうである。植村氏は、現代の"焚書"や創価学会からのいやがらせにあいながらも、別の出版社から出版にこぎつけた。(『前衛』H15.11)
―福島泰照著『創価学会・公明党の解明』の場合―
創価学会からの妨害を予想して、秘密裏に出版作業をおこなった。しかし、本ができあがるころから、大手取次店や広告代理店の扱い拒否という事態に直面し、出版が大幅に遅れた。(『前衛』H15.11)
―隈田洋著『創価学会・公明党の破滅』の場合―
・秘密裏に出版作業がすすめられたが、印刷段階で、印刷業界の幹部から印刷中止を迫られた。印刷所にはいやがらせがつづき、当時の劔木亨弘文相からも中止の圧力がかかったと、著者に伝えられる。この本の場合も古田日大会頭(※日本大学の古田重治郎会頭)からゲラの検閲を迫られた。出版社社長には暴力団員がつきまとい、ついに出版中止となった。(『前衛』H15.11)
・隈部大蔵氏は、西日本新聞社の論説委員をしていたころ、「隅田洋」と名乗り『創価学会・公明党の破滅』という学会批判本を執筆した。すると、昭和43年9月11日、隈部氏は、当時公明党の副委員長であった北條浩に呼び出され、以下のように恫喝(どうかつ)された。(『慧妙』H15.7.16)
●隅田洋著『創価学会・公明党の破滅』という学会批判書の著者である隅田洋を、今日まで半年がかりで探した結果、やっと探し出した。この隅田洋なる者が、ここにいる隈部大蔵その者だ。人違いであるとは、絶対に言わせない。まさか、大きな新聞社の経済社説を担当している論説委員が、学会教義の批判書を書くなどとは想像もしなかった。そんな関係で、隅田洋=隈部大蔵を捜し出すのに予想外に時間がかかってしまったが。
しかしだ。いくらペンネームを用いて学会を批判しようとしても、全国的に張りめぐらされている学会の情報網にひっかからない「虫ケラ」はいないのだ。わかったか。
よく聞いたがよい。たとえていえば、創価学会は「象」それも巨象だ。これにくらべてお前は1匹の「蟻」だ。創価学会を批判する輩に対しては、たとえ1匹の蟻といえども象は全力をもって踏みつぶすのだ(北條浩=総務『もうダメだ!池田大作・創価学会』/『フォーラム21』H16.4.15)
-----------------------
この後、北條総務・副委員長に恫喝された『創価学会・公明党の破滅』は、結局1冊も書店に置かれず「初版即絶版」となった(『フォーラム21』H16.4.15)
●これではまるで、ソビエトで地下出版を出すようなものであろう。私自身、この記事には少々驚き「まてよ、作影(注=池田大作氏の影響の意)はやはり噂だけではなく事実かな」と思わざるを得なかった。というのは、西日本新聞といえばブロック紙の名門、論説委員といえばその最高の地位ぐらいのことはだれでも知っている。しかしその人ですら「極秘」のうちに出版を進める必要があり、見つかればつぶされてしまう。しかもそれに文部大臣が一役買っているのである。文部大臣が自ら言論弾圧に乗り出すとは少々恐れ入った話だが、「作影」が「○影」に波動して文部大臣を動かして論説委員の著書までつぶす、となるとただごとではない(評論家・山本七平著「池田大作氏への公開質問状」『諸君』昭和56年6月号/『フォーラム21』H16.4.15)
―竹中信常著『創価学会』の場合―
著者に創価学会の山崎尚見現副理事長からの電話があった後、ゲラ刷り検閲がおこなわれ、名誉毀損で告訴することもあるとおどされた。
―梶山季之著『小説・創価学会』(女性雑誌に連載)の場合―
梶山氏に抗議の投書が殺到し、雑誌編集長はいやがらせをうけて蒸発するという事態になり、連載を途中でうちきったという。(『前衛』H15.11)
・この他にも、『日蓮正宗創価学会・公明党の破滅』『公明党を折伏しよう』等創価学会に気に入らないとみなされた印刷物の著者や出版関係者がいやがらせをうけ、出版が妨害された事例が次つぎと明らかになった。
<S45>
1.5
・公明党の竹入委員長が記者会見で「事実無根の中傷」と開き直った。
●このことについて竹入氏は「放っておいたほうが良いと進言したが、学会側が工作に動き出し、やむを得ず田中氏に頼んだ。あの記者会見も学会幹部からの強い要請でせざるを得なかった」と周辺に語っている。(『朝日新聞』H10.9.18/『前衛』H15.7)
1.8
・社会党の江田三郎書記長が国会でとりあげることを表明
1.10
・民社党の佐々木良作書記長が国会でとりあげることを表明
1.11
・TBSテレビで放映されていた対談番組「時事放談」で、政治評論家の細川隆元氏が「公明党はナチスに通ずる、今度はこの席に関係者を呼んで問いただす」と発言し、細川氏と小汀利得氏の対談の席に池田大作を迎える特別企画が組まれた。しかし、池田側は、体調不良で多忙という奇妙な理由で出席を拒否した。
1.25
・『朝日新聞』投書欄が、「言論・出版の自由をめぐって」の特集を組む。特集は「『赤旗』が連日キャンペーン記事をのせたため、一般の新聞報道が立ちおくれたため」とことわって、「市民に強い危機意識"出版妨害"の真相求める声」として5投書が紹介され、公明党の「反論は遠慮する」とのコメントまで掲載。
2.2
・マスコミ関連産業労働組合共闘会議(9万7千人)が総評はじめ各労組に呼びかけ、「出版妨害の真相を聞く会」を開催し、21労組が結集
・言論・出版の自由に関する仏教徒懇談会が結成され、各宗各派120人の仏教徒を前に全日本仏教会や東京仏教連合会の代表があいさつ
2.3
・「公明党・創価学会の妨害に反対する、言論・出版の自由にかんする大集会」には3千人が集まった。全国各地でも、言論・出版の自由を守る懇談会が結成された。
2.18~
・特別国会では、社会・民社・共産の各党が、竹入委員長、田中幹事長、池田大作の国会喚問を要求したのをはじめ、基本的人権の1つである言論の自由を侵した創価学会・公明党の危険な体質や、当時、国立戒壇の建立を掲げていた創価学会・公明党の政教一致問題等について厳しい追及を加えたのだった。
3.17
・衆院第1議員会館で出版妨害事件真相究明議員集会が開かれた。([画像])
<自民党にすがって弾圧回避>
●池田会長は自らの国会喚問を阻止するために衆参両院の公明党国会議員を総動員し、赤坂2丁目のクラブ「石丸」などを拠点に、各党の理事を接待責めにして懐柔する工作をおこなった。さらに、池田会長は佐藤(※栄作首相)にも連絡を取っていた。70年1月30日の『佐藤日記』には、岩佐富士銀行頭取を通じて「藤原弘達問題には干与しな[い]様に」という池田からの伝言が記され、佐藤は「同感」と岩佐に伝えている(『佐藤日記(4)』31頁)。野党などから出された池田喚問要求について佐藤はのらりくらりと対応し、結局これをうやむやにしてしまう。池田の伝言どおり、「干与しない」ように行動したのである。(『前衛』H15.7)
●69年末に表面化した言論出版妨害問題のときは、佐藤栄作首相と自民党幹事長をしていた田中さんには、助けられ、感謝している。終生忘れない。国会では罵詈雑言を浴びせられ、ほかにだれも助けてくれる人はいなかった。
創価学会批判の本が出るというので、私が田中さんに頼んで仲介に動いてもらったのだが、田中さんは追及されると、「竹入に頼まれたのではない。幹事長だから勝手におせっかいをやいているだけだ」と釈明していた。これには感激した。家の周りは、新聞記者に囲まれて出られない。電話で連絡を取った。
「ここも新聞記者でいっぱいで出られないぞ」
「すまんなあ」
「いいよ、幹事長やめりゃあいいんだから」
「それじゃあ、こっちも委員長やめなくっちゃあ」
「いやあ、まあまあ、成り行きだ。こんな泥沼、いつでもあるんだから」
こんなやりとりをしたのを思い出す。
佐藤さんは、関係者の証人喚問要求に、のらりくらりと時間かせぎをしてくれた。国会の委員会採決も先送りしてくれるなどいろいろ配慮してくれた。(竹入義勝=公明党元委員長「竹入秘話」『朝日新聞』H10.8.26/『前衛』H15.7)
●当時、池田大作氏は「田中さんのためなら公明党をつぶしてもいい」とまで言ったそうだ。田中は年1回の公明党の青年研修会で講演して帰ってくると、私に池田氏がああ言ったとかこう言ったとか、全て話してくれた(佐藤昭子=田中秘書『私の田中角栄日記』75頁/『前衛』H15.7)
-----------------------
この言論出版妨害事件を契機に、田中と竹入の間は一段と深まった。(『前衛』H15.7)
<S45.5.3>
◆……今回の問題は、あまりにも配慮が足りなかったと思う。また、名誉を守るためとはいえ、これまで批判に対してあまりにも神経過敏にすぎた体質があり、それが寛容さをかき、わざわざ社会と断絶をつくってしまったことも認めなければならない。……今後は2度と、同じ徹を踏んではならぬと、猛省したいのであります。……言論の自由が、幾多、先人の流血の戦いによって勝ち取られたものであり、……これを侵すことは民衆の権利への侵害であることを明確に再確認し、言論の自由を守り抜くことを私どもの総意として確認したいと思いますがいかがでしょうか(池田大作「第33回本部総会」『聖教新聞』S45.5.4/『フォーラム21』H14.12.15)
-----------------------
まさにその同時期、一方で、山崎正友・同会顧問弁護士をリーダーとする謀略軍団は、同事件で追及の先頭に立っていた日本共産党の宮本顕治委員長宅への電話盗聴の工作に着手していたのである……。
◆また、学会は、公明党の支持団体ということになります。とうぜん学会員の個人個人の政党支持は、従来通り自由であります。学会は日蓮大聖人の御本尊を信奉する宗教団体であって、政党支持については、会員の自由意思にまかせ、まったく干渉するものではありません(池田大作「第33回本部総会」要旨/『フォーラム21』H15.7.15)
―常態化する歴史の偽造―
(本誌編集部『フォーラム21』H18.6.15)
創価学会による歴史偽造は、いまに始まったことではない。69年末から70年にかけての言論出版妨害の問題もそうである。このとき、池田大作氏は70年5月3日の本部総会で「お詫び講演」をした。言論出版妨害を事実として認め、「今後は、2度と、同じ轍を踏んではならぬと猛省したい」とまで述べた。政治・政党との関係については「政教分離でいけばよいと思う」と述べ、共産党への態度にも言及して「我々は、かたくなな反共主義を掲げるものではない」と述べた。
つまり、言論出版妨害への社会的批判を受け入れて、全面謝罪したのである。にもかかわらず、創価学会はいま、あれは学会婦人部が侮辱されたからだとか、信教の自由を守る正義の戦いだったと描いている。
実は、「お詫び講演」の前後、学会内部ではとんでもない事態が進行中だった。
1通の内部文書がある。70年3月4日付の「総合本部長会報告」。学会副理事長らが地方幹部を相手におこなった指導メモである。こんな指導がされていた。
「(言論問題の)本質は広布を阻む第六天の魔である」「公明党・創価学会の悪口を一口でもいったら追かえし、不法侵入として警察へ訴える位にする」
「マルキョウ(丸の中に共の文字。以下同)は槍傷覚悟でやって来る。広布をハバむ魔である。重大な決意をしなければならない」「マルキョウに焦点を合すこと」「マルキョウをつぶす様祈っていこう」
当然のことながら、マルキョウは共産党のことだ。表向きの「お詫び講演」の裏では、こんな態勢がとられていた。そして講演直後の70年5月から7月、その一部が実行されている。宮本宅電話盗聴である。これが創価学会の組織的犯罪であることは、東京高裁の確定判決(88年4月)で明らかになっている。
そしていま、「反共主義をとらない」どころか、選挙では共産党などの候補者や運動員をとり囲んで妨害し『聖教新聞』などでは「日本中が大嫌悪」「デマ・不祥事で総すかん。“時代遅れ“のジリ貧党」と、「文明論」にはほど遠い悪罵をくり返しているのである。
ところで、宮本宅電話盗聴の真相がわかったのは80年。山崎正友・学会元顧問弁護士の告白によってである。その間、創価学会はそんな事実をひた隠しにしたまま、共産党との間で「文明論」を語り、「協定」まで結んでいた。
とはいえ、「協定」の文書は現に存在している。池田氏も直接かかわったこの文書にケチをつけることはできない。それを反故にするには、誰かを“犯人“に仕立て上げざるをえない。――『創価新報』の歴史偽造には、そんな背景事情が透けて見えるようだ。
一方、共産党は盗聴の真相を知らなかったとはいえ、「反共主義はとらない」などという発言を本気で信じていたのだろうか。政党が特定宗教と「協定」することの検討を含め、全面的な総括はまだされていない。
■ソフト化しても続く「仏敵たたき」なぜ
(創価学会取材班『AERA』H16.12.13抜粋)
『聖教新聞』の名物コーナーに、学会幹部らによる座談会記事がある。"敵"のスキャンダルをあげつらったり、罵詈雑言を浴びせたり、刺激的な内容になることが多い。(中略)
【「休質」転換どこまで】
11月中旬、国会近くで反学会色の強い集会があった。そこで、共産党議員がこう言った。
「創価学会は巨大な宗教法人であると同時に、今や公明党が政権に入り、単なる1つの団体では済まされなくなった」
そう考えるのは、反学会勢力だけだろうか。学会の立場や影響力が大きく変わったのに"敵"に牙をむき続けていれば、一時的に批判勢力を牽制できたとしても、むしろ、社会に「声なき反感」を広げてしまうかもしれない。
70年の「政教分離」宣言のとき、池田氏は、
《社会に信頼され、親しまれる学会》
とのモットーを掲げ、こう戒めている。
「批判に対してあまりにも神経過敏すぎた体質があり、それが寛容さを欠き、社会と断絶をつくってしまったことを認めなければならない。今後は2度と同じ轍を踏んではならないと猛省したい」
当時、池田氏が指摘した「体質」は転換できたのだろうか。
先の座談会記事をめくってみると、実にさまざまなフレーズを使って"敵"を攻撃していることに目を奪われる。
「薄汚いドブネズミ」「淫獣坊主」「『人問失格』の見本」「支持者をナメた畜生議員「ゴキブリ坊主」「老いぼれたクズ同然の穀潰(ごくつぶ)し」「極悪ペテン師」「袈裟を被った鬼畜」……。
その矛先は、相手の家族にまで及ぶこともある。
「底なしの銭ゲバ女房」「親父譲りの逆上男」……。



(平静丸『前衛』H15.11編集)
<クロをシロと描いて「真実」の名で「書き残す」>
************************************************************
◆現在、小説が描く時代は、昭和45年―会長就任10周年の5月3日からの新生の旅立ちである。当時の学会は、"言論問題"の嵐の渦中にあった(随筆「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.8.8)
◆私には、書かねばならない使命と責任がある。後輩に真実を伝えなければならない(随筆「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.8.8)
◆「真実」を明確に書き残すことが、未来の人びとの明鏡となる。真実は、語らなければ残らない。沈黙は闇を増すだけだ。ゆえに私も、書くべきことは全部、書き残す責任がある(随筆「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.8.8)
------------------------------------------------------------
1970年の「5月3日」とは、創価学会の起こした言論・出版妨害事件について池田氏本人が"猛省"を表明した日であり、創価学全と公明党との分離や「かたくなな反共主義を掲げるものではない」ことなどを国民に約束した日でした。連載小説では、"言論問題"は創価学会を陥れる謀略事件だったかのように描き、表むき「お詫び」しながら、裏で日本共産党への盗聴をおこなったことは隠しとおす、「反共主義を掲げない」など言ったこともないというような展開になっています。クロをシロと描いて居直り、それを「真実」の名で「書き残す」ものといわなければなりません。
<"言論問題"とは何だったか>
1969年11月、藤原弘達著『創価学会を斬る』が出版されました。この本の「まえがき」で藤原氏は、出版にあたって創価学会・公明党から妨害を受けていたことを明らかにしました。一部週刊誌も、この「まえがき」を取り上げました。この直後のNHK総選挙特集番組「2党間討論(公明党-共産党)」で、日本共産党の松本善明氏が、公明党の正木良明氏に、この問題をつきつけたところ、正木氏は「すべてウソです」と答えました。
これに怒った藤原氏は、『赤旗』で、田中角栄自民党幹事長が公明党の竹入委員長の依頼で、この本を世に出さないためにさまざまな働きかけをしていたことを暴露しました。創価学会が組織的に印刷、広告、取次店から小売店まで、圧力をかけたことも明らかになりました。国会では、共産党をはじめ野党各党がこの問題をとりあげました。『赤旗』の創価学会・公明党の言論・出版妨害追及キャンペーンは言論界、出版界を動かし、学者・文化人は「言論・出版の自由にかんする懇談会」を結成して、真相究明を本格化させました。
この「懇談会」によって、いくつかの具体的事例が明らかになっています。
内藤国夫著『公明党の素顔』(エール出版社)の場合は、67年1月ごろから、三一書房からの執筆依頼で、都庁担当新聞記者として取材してきた都議会公明党の素顔を書きはじめたということです。これが創価学会・公明党の知るところとなり、出版社に圧力がかかり、出版計画は中止となります。内藤氏は出版社を変更し、極秘裏に出版準備をつづけましたが、印刷工程でゲラが創価学会にわたった(業務上横領の疑い)ようで、公明党の竹入委員長が30数箇所の書き換えや削除を要求してきました。さらに、国際勝共連合の背後にいた右翼の頭目の笹川良一が内藤氏に「わしは公明党に前に一度恩を受けている。本はおれが全部買いたい」といってきたことも明らかにされました。この本は69年5月に出版されましたが、大手取次店は配本を拒否し、小売店に宣伝して注文をとるという方法で、わずかに世に出されました。
元創価学会員の植村左内氏の著作『これが創価学会だ』の場合は、まだ本が出ないうちに、池田会長と竹入委員長が出版社を相手どり、図書発行等禁止仮処分申請をおこないました。東京地裁が、まだ本ができていないことを理由に申請を却下すると、今度は名誉毀損として告訴しました。この本も取次店が扱いを拒否しました。68年12月には、出版社と創価学会・公明党の間に示談が成立し、出版社は著者に無断で印刷過程のすべてを創価学会・公明党にわたしてしまいました。出版社への圧力には、福田赳夫、賀屋興宣という自民党中枢が関与し、宗教センター理事長で日本大学会頭の古田重二良氏が示談をまとめたということです。庭野日敬立正佼成会会長(当時)によれば、古田氏は、立正佼成会に買い取られて配られた本を信者から取りもどし、日大校庭で焼いてしまったそうです。植村氏は、現代の"焚書"や創価学会からのいやがらせにあいながらも、別の出版社から出版にこぎつけました。
福島泰照著『創価学会・公明党の解明』の場合は、創価学会からの妨害を予想して、秘密裏に出版作業をおこないました。しかし、本ができあがるころから、大手取次店や広告代理店の扱い拒否という事態に直面し、出版が大幅に遅れました。
隈田洋著『日蓮正宗・創価学会・公明党に破滅』の場合も、秘密裏に出版作業がすすめられましたが、印刷段階で、印刷業界の幹部から印刷中止を迫られました。印刷所にはいやがらせがつづき、当時の劔木亨弘文相からも中止の圧力がかかったと、著者に伝えられます。この本の場合も古田日大会頭からゲラの検閲を迫られました。出版社社長には暴力団員がつきまとい、ついに出版中止となりました。
竹中信常著『創価学会』の場合は、著者に創価学会の山崎尚見現副理事長からの電話があった後、ゲラ刷り検閲がおこなわれ、名誉毀損で告訴することもあるとおどされました。
梶山季之氏は、ある女性雑誌に『小説・創価学会』を連載していましたが、梶山氏に抗議の投書が殺到し、雑誌編集長はいやがらせをうけて蒸発するという事態になり、連載を途中でうちきったということです。
この他にも、創価学会に気に入らないとみなされた印刷物の著者や出版関係者がいやがらせをうけ、出版が妨害された事例が次つぎと明らかになりました。
<言論・出版・表現の自由をまもる国民的たたかい>
こうした創価学会・公明党の陰険でファッショ的な言論・出版妨害にたいして、民主主義をまもるたたかいが短期間に広がりました。
1969年12月17日付『赤旗』に藤原弘達氏が登場し、新事実をふくむ出版妨害の詳細が報じられると、作家の臼井吉見氏らも「私もいやがらせをうけたことがある」と述べ、これまで創価学会・公明党の反民主主義的体質に危惧をいだいていた言論人や宗教家が立ち上がりました。日本ジャーナリスト会議、全国出版産業労働組合総連合会、日本新聞労働組合連合、文化団体連絡会議などが、言論・出版妨害の真相究明と創価学会・公明党への抗議を表明しました。岩波書店の玉井乾介編集部長、未来社の西谷能雄社長、飯塚書店の飯塚広社長、文理書院の寺島徳治社長なども、言論の自由の重要性を訴えました。
ロシア文学者の草鹿外吉氏ら5氏のよびかけで、12月23日に「言論・出版の自由にかんする懇談会」がひらかれました。懇談会は「憲法第21条で保障されている『言論、出版その他一切の表現の自由』をはなはだおかす……行為を断じて許すことができません」との「声明」を発表し、この「声明」への文化人・知識人の賛同が年末年始の時期に333名になり、その後、「言論・出版の自由にかんするシンポジウム」が開かれました。
1月5日、公明党の竹入委員長が記者会見で「事実無根の中傷」と開き直ったために、いっそう大きな憤激が全国をかけめぐりました。8日には社会党の江田三郎書記長が、10日には民社党の佐々木良作書記長が、国会でとりあげることを表明しました。1月11日、TBSテレビで放映されていた対談番組「時事放談」で、政治評論家の細川隆元氏が「公明党はナチスに通ずる、今度はこの席に関係者を呼んで問いただす」と発言し、細川氏と小汀利得氏の対談の席に池田大作氏を迎える特別企画が組まれました。しかし、池田氏側は、体調不良で多忙という奇妙な理由で出席を拒否しました。『朝日新聞』1月25日付の投書欄は、「言論・出版の自由をめぐって」の特集を組みました。特集は「『赤旗』が連日キャンペーン記事をのせたため、一般の新聞報道が立ちおくれたため」とことわって、「市民に強い危機意識"出版妨害"の真相求める声」として5投書が紹介され、公明党の「反論は遠慮する」とのコメントまで掲載されています。
2月2日、マスコミ関連産業労働組合共闘会議(9万7千人)が総評はじめ各労組に呼びかけ、「出版妨害の真相を聞く会」を開催し、21労組が結集しました。同日、言論・出版の自由に関する仏教徒懇談会が結成され、各宗各派120人の仏教徒を前に全日本仏教会や東京仏教連合会の代表があいさつしました。翌日の3日にひらかれた「公明党・創価学会の妨害に反対する、言論・出版の自由にかんする大集会」には3千人が集まりました。全国各地でも、言論・出版の自由を守る懇談会が結成されました。
国会では、年末の総選挙で4議席から14議席に躍進した日本共産党を代表して、2月18日の衆院本会議で米原昶議員が出版妨害事件をとりあげ、27日の衆院予算委員会総括質問にたった不破哲三議員は、公明党の大野潔副書記長が日本テレビに藤原弘達氏の出演を手びかえてほしいと申し入れたことなど、新事実をしめして、追及しました。
3月17日には、共産、社会、民社、自民の各党から130数議員が「出版妨害問題真相究明議員集会」をひらきました。
創価学会側は、猛烈な反共攻撃で、世論の分断と批判封じをねらいました。この時期の『聖教新聞』には、「圧迫される自由」「踏みにじられる国家主権」「醜い権力闘争」「冷酷な粛清」「暴力革命」などといった、旧ソ連、中国の文化大革命、反動勢力の戦前からのデマ宣伝などを題材とする大見出しの反共記事が、見開きで何回も特集されています。
この反共攻撃が『赤旗』によって論破しつくされ、創価学会の反民主主義的体質はさらに赤裸々となり、創価学会員からも「べールはぎ末端の信者救ってほしい」「バチの恐怖心から抜け出そう」などの声が『赤旗』にとどくようになりました。言論界・出版界は、創価学会批判を回避する「鶴タブー」(創価学会は日蓮正宗信徒団体だった当時は宗門の紋の鶴をマークにしていました)を打ち破りました。
こうして、池田会長が「名誉を守るためとはいえ、これまでは批判に対して、あまりにも神経過敏にすぎた体質があり、それが寛容さを欠き、わざわざ社会と断絶をつくってしまったことも認めなければならない。今後は、2度と、同じ轍を踏んではならぬと、猛省したいのであります。私は、私の良心として、いかなる理由やいいぶんがあったにせよ、関係者をはじめ、国民の皆さんに多大のご迷惑をおかけしたことを率直にお詫び申し上げるものであります。もしできうれば、いつの日か関係者の方におわびしたい気持ちでもあります」と、"猛省"講演をするにいたったのでした。『聖教新聞』70年5月4日付は、「言論・出版問題、同じ轍、2度と踏まぬ、猛省して"自由"を厳守」、「学会と公明党の関係、明確に分離の方向」という見出しでこの講演を報じ、講演は、創価学会の教学機関誌『大白蓮華』70年6月号にも掲載されました。
<"言論問題"を「選挙妨害」「捏造」「謀略」と描く>
************************************************************
昭和45年の"言論問題"の前後より、学会は、数人の代議士からも罵倒され、ある時は、テレビを使い、雑誌を使い、演説会を使い、非難中傷された。・・・「信教の自由」を侵害する凶暴な嵐であった。理不尽な罵倒の連続であった。ともあれ、・・・断固として仏敵と戦う決意を、炎と燃やした。・・・正義の信仰を流布して、何が悪いのか! 信教の自由ではないか!(随筆「新・人間革命」/『聖教新聞』H13.7.10)
------------------------------------------------------------
この随筆「新・人間革命」にたいして、徹底的な批判をくわえたのが、不破哲三日本共産党議長の論文「創価学会・池田大作氏に問う―31年前の『猛省』は世をあざむく虚言だったのか」(『しんぶん赤旗』H13.7.22)でした。不破論文は、次のように、本質を深くえぐりだしました。
「この告白が創価学会と公明党の本音だとすれば、この集団は、本音をおしかくした巨大な虚言によって、31年にわたって日本の国民と世論をもてあそんできた、ということになります。いったい、この集団は、日本の社会と国民そのものを、何と考えているのか、そのことがあらためて問われるではありませんか。……なかでも、私がとりわけ重要だと思うことは、"自分たちは、どんな無法なことをやってもいっも『仏』、それを批判するものはすべて『仏敵』だ"という究極の独善主義―以前、『邪宗撲滅』を前面に押だししていた時期にむきだしの形で現れ、社会的な批判の的となった独善主義が、この文章のなかに、まるごと復活していることです。……自分たちを批判するものにすべて『仏敵』のレッテルを張り、手段を選ばずその『撲滅』をはかるという組織は、現代の民主主義のもとでは、政治の世界でも、宗教の世界でも、存在の資格を疑われても仕方のないものです」。
************************************************************
◆あらゆる手を使っての執拗な攻撃である。この機会に、なんとしても学会に大ダメージを与えたいと、血道をあげていたのだ(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.7.5)
------------------------------------------------------------
自らを省みるどころか、あろうことか言論・出版妨害を批判した人々にすべての責任を転嫁し、自分たちの犯罪行為を免罪する「独善主義」に依然としてしがみついています。
<学会批判は「正義の指導者を倒さんとする弾圧」>
************************************************************
◆懸命に総選挙の支援活動に取り組んできた学会員は、「公明党大勝利」に沸き返った。……実は、藤沢達造という政治評論家が書いた、創価学会批判書の出版を、学会と公明党が妨害したという非難が沸騰するなかでの、支援活動であったのである(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.6.2)。
◆(藤原弘達著『創価学会を斬る』の出版が)衆院選挙を前にした、悪質な妨害といってよかった(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.6.5)
◆"これは、言論の自由をいいことに、嘘と罵詈雑言で塗り固めた、誹謗・中傷のための謀略本ではないか。言論の自由を利用した言論の暴力以外の何ものでもない"(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.6.6)
◆1969年(昭和44年)は、衆院の解散、総選挙が予測されていた。民社党の国会議員が、公明党の批判書を出したのも、この年であった。また全国紙の記者の工藤国哉、福山泰之を名乗る地方紙の論説委員の隈田専蔵らも相次ぎ批判書を出版した。……ともあれ、衆院選前に、藤沢達造の本とともに、陰険な批判本が次々と出されたのだ。暗黒の嵐が、正義の城に吹き荒れた。その卑劣な風とともに、正義の指導者を倒さんとする、攻撃の毒矢が放たれたのであった(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.6.25)
◆弾圧は、「社会的な問題」を探し出し、時には捏造して罪を被せ、それを理由にして起こるのである(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.7.9)
------------------------------------------------------------
「選挙を前にした、悪質な妨害」「嘘と罵詈雑言で塗り固めた、誹謗・中傷のための謀略本」が事実であったとしても、権力や暴力を使って出版社や筆者に圧力をかけてよい、などという道理は全くない。自分達が行った言論弾圧を棚に上げて、学会批判を「弾圧」「正義の指導者を倒さんとする、攻撃の毒矢」などと批判するとは、盗人猛々しいというしかない。しかも、当時は、自らの行為を猛省していたのであるから、二重に罪が重い(法蔵)。
<言論弾圧を過小評価>
************************************************************
◆出版関係の業務に携わっているメンバーのなかに、取次店や書店で批判書の非道さを訴え、取り扱いの配慮を要請した人はいたようだ(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.7.10)
◆悔しさと怒りに震える学会員の抗議には、強い語調の電話や、論旨に飛躍が見られる文面もあったかもしれない(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.7.10)
------------------------------------------------------------
「配慮を要請」などというものでなかったからこそ、国会内外で大問題になったことを、何と心得ているのでしょうか。言論・出版妨害は、自分たちへの批判を封ずるために、自民党首脳を動かし、右翼の大物から暴力団まで介在させたファッショ的な謀略であり、創価学会の底知れない反民主主義的体質のあらわれだったのです。
************************************************************
◆もし、喧伝されたように、学会員が、脅迫じみた言動をとれば、さらに学会に非難が集中することは自明の理である。そんな学会を貶(おとし)めるようなことを、あえて学会員がするとは、どうしても考えられなかった。脅迫電語や脅迫状があったとするなら、学会への反発や敵意を高めさせるための謀略かもしれない。しかし、困ったことには、それを証明する手立てはなかった(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.7.11)
------------------------------------------------------------
学会員による批判者への常軌を逸したイヤガラセは、現在も続いており枚挙に暇がない(資料参照)。さらに、これがエスカレートし、警察沙汰になって逮捕された者もいるのである(資料参照)。こうした事実から考えても、学会員によるイヤガラセであったことは間違いない。しかも、当時は社会や関係者に対して猛省しておきながら、今頃になって「学会への反発や敵意を高めさせるための謀略」とは、呆れてものが言えない(法蔵)。
◆創価学会は、1963年7月、「創価学会批判のマスコミや言論人に向けて、何通もの非難攻撃の手紙を書き、投函すること」(吉良陽一『実録 創価学会=7つの大罪』)を役割としで担う言論部なる部隊を組織しました。この言論部の第1回大会(64年)で池田会長は、次のように扇動しています。「私どもの執念深い、……情熱ある言論戦を展開して、悪い彼らが、いままでは思い上がり、独断的であり、利己主義である彼らを恐れさせて、身ぶるいさせて、ほんとうに正しい言論戦はこわい、どうしようもないというところまで、追って追って追いまくっていこうではありませんか」(『会長講演集』第9巻)
-----------------------
批判者へのイヤガラセは「学会への反発や敵意を高めさせるための謀略」どころか、学会上層部による組織的な謀略ではなかったのか、とさえ思える(法蔵)。
<"猛省"はなかったことに>
************************************************************
「関係者をはじめ、国民の皆さんに、多大なご迷惑をおかけしたことを、率直にお詫び申し上げるものでございます」伸一は頭を下げた(小説『新・人間革命』/『聖教新聞』H15.7.16)
------------------------------------------------------------
不破論文もあって、言論出版妨害で批判を受けた事実そのものを否定することはさすがにできません。しかし、「お詫び」を口にしてはいますが、池田講演にあった「2度と、同じ轍を踏んではならぬと、猛省したいのであります」の部分はそっくり削除されています。
************************************************************
参加者は驚きを隠せなかった。"先生がなぜ謝らなければならないのだ! ""学会は法に触れるようなことなど何もやっていないではないか!"。複雑な表情で壇上を見上げる人もいれば、悔し涙を流す人もいた。ある人は、学会の会長として、すべて自分の責任ととらえ、真摯に謝罪する伸一の姿に、申し訳なさと感動を覚えながら、心に誓った。……そして、社会を大切にし、大きな心で人びとを包む寛容さを、会長は身を持ってしめしたのだと思った(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.7.16)
------------------------------------------------------------
ここには、言論・出版妨害という民主主義と絶対に相容れない暴挙そのものにたいする反省など微塵もみられません。むしろ、正当な行為にたいする世間の不当な誤解にもかかわらず、責任を一身にひきうけて「謝罪」でこたえた池田会長の「寛容」にたいする賛美へと、問題がすっぽりすりかえられています。「謝罪」は、その道具立てにされてしまっているのです。重ねて、言論・出版妨害という反民主的犯罪行為を否定し、居直る―ここに、連載小説のこのくだりの本質があるといって間違いないでしょう。
そのことは、池田"猛省"講演をしておきながら、創価学会が反民主主義体質を温存、エスカレートさせてきた事実によっても、裏付けられるでしょう。1999年には、自民党代議士の著作で創価学会・公明党に言及した部分が、創価学会の策動によってゲラ刷り段階で削除されたという事実もありました。東京では、97年3月7日に中央区議会で田畑五十二区議、2000年3月13日に大田区議会で田口仁区議、翌年3月23日に中央区議会で佐藤孝太郎区議と、公明党区議が予算委員会で「区立図書館の蔵書に創価学会批判書がある」と排斥を要求し、図書館人事に介入する発言が相次ぎました。『聖教新聞』2002年12月27日付は、青年部体制強化の一環として、青年部のなかにも「破邪顕正の先駆」を任務とする言論部が設置されたと発表しています。
この年末の時期には、『拉致被害者と日本人妻を返せ北朝鮮問題と日本共産党の罪』という反共謀略本が出版され、今春のいっせい地方選挙では、関東を中心に、この本の電車の中吊り広告という形で、日本共産党への大々的な誹謗中傷がおこなわれました。この反共謀略本は著者も出版元も創価学会員であり、この本を創価学会が組織的に買い取って配布したことも、『しんぶん赤旗』の調査で明らかになっています。現在の創価学会が、言論抑圧にとどまらず、謀略的な反共・反民主主義の反社会的集団へといっそう進化していることは多くの人の知るところです。
<政教分離の虚々>
言論・出版妨害事件の究明は、創価学会・公明党の政治進出のねらいが、政教一体による創価学会の国教化と池田氏の"天下取り"にあり、そのために批判者を排除しようとしたものだ、という本質に迫りました。池田"猛省"講演が、国立戒壇の否定、創価学会と公明党の関係での分離の方向などを口にせざるをえなかったのは、世論のこうした包囲によってでした。"猛省"講演を掲載した『聖教新聞』70年5月4日付は、「学会と公明党の関係、明確に分離の方向」と見出しにかかげ、創価学会の教学機関誌『大白蓮華』70年6月号にも掲載されました。
************************************************************
◆(憲法の政教分離とは)国は宗教に対して中立の立場をとり、宗教に介入してはならないことを示したものであり、宗教団体の政治活動を禁じたものでは決してない(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.6.13)
◆創価学会と公明党の関係は、もともと憲法が禁ずる"政教一致"とは、全く異なるものである(小説「新・人間革命」/『聖教新聞』H15.6.13)
------------------------------------------------------------
創価学会と公明党との分離を公約する必要などさらさらなかった、というのです。"猛省"講演後、たしかに国立戒壇はおろし、一時期、創価学会と公明党とをそれなりに区別する動きはありました。しかし、その後、創価学会・公明党の政教一体がますますエスカレートしてきたことは、選挙のたびに繰り広げられる創価学会の総動員をみるだけであきらかです。2002年4月には、創価学会は会則を変更して、第45条に「社会問題についての見解ならびに国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の本部にそれぞれ社会協議会を置く」としたのです。宗教法人の会則に「選挙に関する対応」の条項をかかげるにいたりました。「王仏冥合」も、今年から刊行されている池田大作述『御書の世界』にみるように、政界はもとより行政、外交、司法、経済、文化、マスコミなどに創価学会員をおくりこむ意味に拡大されて、使われています。
創価学会が、露骨な政教一体への批判者を「宗教弾圧」とまで居直る根底に、社会と国民への約束をかなぐり捨てて恥じないこの団体の反民主的、反社会的本質があることを、改めてきびしく指摘しないわけにいきません。
◆政教一体が間違っている理由としてあげられるのは、それによって信者は、政党選択の自由だけではなく、政策論議の自由も、政策選択の自由も失ってしまうからである。宗教的権威が、宗教団体と政党の双方に貫通しているのだから、そこでは、民主的な討論を生む民主主義の基盤が育たない(日隈威徳著『宗教と民主政治』)



―事実を隠蔽し歴史の塗り替え企む―
―「言論・出版妨害事件」を無かったことに―
―悪書『新・人間革命』は偽りの歴史書だ!!―
(『慧妙』H15.7.16)
池田創価学会による、大規模な歴史改ざんが始まった。
池田創価学会による過去の改ざんは、例えば池田の入信にまつわる話や、池田大作と戸田会長との関係についてなど、池田が会長に就任して以来、これまでずっと続けられてきていたが、ここにきて学会はついに、社会的大事件となった、あの有名な「言論・出版妨害事件」まで、その内容を自分達の都合のいいように改ざんして『聖教新聞』に掲載する、という露骨なことを始めたのだ。
その呆れた改ざんに鉄槌(てっつい)を下す!
『聖教新聞』に連載されている『新・人間革命』。そのうち、本年5月5日付に始まり7月11日付で終わった「烈風」の章に、「言論・出版妨害事件」(以下「事件」と略す)が書かれている。
以下、この章の最終部分(第55回~第57回)に載った「事件」の総括につき、逐条的(ちくじょうてき)に学会の欺瞞(ぎまん)を粉砕していくことにする。
<「政教分離は以前からの懸案」!?>
―学会は一貫して公明党を支配―
************************************************************
(※「事件」が起きる前から)新時代に飛翔するために、学会は、機構の改革を推進していた。
「政教一致」などという批判は、その機構の整備が進みつつあることを知ったうえで、改革途上ゆえの未整理な部分を、あえて突き、攻撃材料としたのかもしれない。
山本伸一は、日蓮大聖人が流罪の地・佐渡でお認(したた)めの『開目抄』に「世間の失(とが)に寄せ」(※御書571頁)との一節があることを思い起こした。
弾圧は、「社会的な問題」を探し出し、時には捏造(ねつぞう)して罪を被(かぶ)せ、それを理由にして起こるのである。(中略)
伸一は、今回の問題が意図的に仕掛けられた問題であったとしても、結果的に社会を騒がせてしまったことに、会長としての責任を感じていた。
彼は、批判書をめぐる学会の対応について、社会という観点から冷静に分析を重ねていった。(『新・人間革命』「烈風」)
------------------------------------------------------------
まず、この〝伏線〟から粉砕していこう。
池田は、「新時代に飛翔するために、学会は、機構の改革を推進していた」というが、少なくともそれは、「政教一致」の状態を解消しようとする改革でなかったのは確実。その証拠に池田大作は、「事件」についての謝罪講演を行なった翌々日、昭和45年5月5日の「社長会」の席上で、次のような発言をなしているのだ。
●竹入に、今まで以上に王仏冥合(おうぶつみょうごう)・政教一致でゆけ、と云おうか。(池田大作「社長会」S45.5.5)
●5月3日が終われば、山は過ぎた。5月3日は勝ちだな。(池田大作「社長会」S45.5.5)
まったく無反省。池田は「政教一致」を改めるつもりなど、もとよりなかったのだ。また、元公明党委員長の竹入義勝氏は、自分自身が公明党の委員長を務めていた頃をふり返り、学会・公明党の政教一致の実態について、次のように記(しる)している。
●委員長を引き受けるときから人事権は学会にあると、明確にされていた。選挙にしても人事にしても、党内はみな学会を向いている。(中略)公明党は財政、組織の上で創価学会に従属していた。『公明新聞』や雑誌『公明』も学会の意向が大きなウェイトを占め、部数は学会の意向で決められてしまう。党員数も前年数値を参考に調整して決めていた。(竹入義勝=元公明党委員長『朝日新聞』H10.9.17)
このように、創価学会による公明党支配、すなわち「政教一致」の状況は、「事件」以降もずっと続いていたのであり、それを全否定するような大ウソをまともに信じるのは、洗脳されきった学会員以外にはいないであろう。
また、後述するが、そもそも、「事件」は創価学会が組織ぐるみで起こしたものである。それを誰かが「捏造して罪を被(かぶ)せ」たとか「意図的に仕掛けられた」などと言うのは、欺瞞(ぎまん)以外の何ものでもない。
<「事件」矮小化に腐心する学会>
―実態は自民首脳も使った大醜聞―
************************************************************
秋月栄介(※秋谷栄之助のこと)らが、著者の藤沢達造(※藤原弘達氏のこと)や出版社の関係者に会い、内容についての申し入れを行なったが、そのどこに問題があったのだろうか。
秋月は、事前の話し合いで解決できるものならと考えて、行動したのであろう。
秋月らは、あくまでも要請を伝えたにすぎず、その言い方も丁重であり、妨害の意図など全くなかった。
だが、本の出版前に接触をもったということ自体が問題とされたのだ。(中略)
事前に接触したことが攻撃の口実にされ、言論を抑圧したかのような誤解を社会に与えてしまったのだ。(『新・人間革命』「烈風」)
------------------------------------------------------------
いよいよ「事件」そのものの改ざんであるが、ここで、まず「事件」の経過を、藤原行正著『池田大作の素顔』を元に、時系列に整理しておく。
昭和44年8月末、藤原弘達氏が「この日本をどうする」という警世キャンペーンシリーズの第1巻として、『日本教育改造法案』を出版。その車内吊り広告の脇に、次回作『創価学会を斬(き)る』の出版を予告
これを知った池田大作は、藤原弘達氏と面識のあった、公明党東京都議の藤原行正氏に、出版差し止めの交渉をするよう命ずる。
命を受けた藤原行正氏は、同年8月31日、著者の藤原弘達氏宅を訪ねるも、交渉は不調に終わる
9月4日、藤原行正氏は、出版社である日新報道に出版中止を掛け合うが、これも不調
9月14日、今度は秋谷栄之助と藤原行正氏が藤原弘達氏と面談。1時間45分に及び交渉するが、やはり不調に終わる(この時の会談の内容は藤原弘達氏によって録音され、後に公表されることとなる)
同時期、池田大作は、後にリクルート事件で有名になる池田克也(当時は潮出版社勤務)に命じ、大手書籍取次店や大手書店に圧力をかけさせる。その直後、藤原弘達氏は、前述の録音テープの存在をマスコミに流す
対応に窮(きゅう)した池田大作は、竹入義勝氏よりの進言を容(い)れ、当時の自民党幹事長・田中角栄氏にもみ消しを依頼する
田中角栄氏はまず、10月6日に藤原弘達氏に架電。
次いで10月15日、赤坂の料亭に藤原弘達氏を呼び出し交渉。この時、隣の部屋で、交渉の行方に聞き耳を立てている池田大作と竹入氏の姿を、料亭の仲居が目撃。後にサンケイ新聞がその事実をスッパ抜く。
さらに10月23日、田中角栄氏が再度、藤原弘達氏と面談するが、結局すべて不調に終わる
11月上旬、『創価学会を斬る』が出版される
12月、衆院選の公示と前後して週刊誌が「事件」を報道。その後、藤原弘達氏が日本共産党と接触。17日より始まった『赤旗』の糾弾(きゅうだん)キャンペーンにより、「事件」に現職・自民党幹事長が関与していたことが表面化し、「事件」は一気に社会問題化する
『新・人間革命』では、「事件」を、藤原弘達氏の著書に対する出版中止、ないしは内容の変更を、学会幹部が求めたというだけの話であるかに矮小(わいしょう)化しているが、実際の「事件」は、藤原弘達氏に限っただけでも、これほど大規模。
さらに、「事件」の全容は、藤原弘達氏に加え、ジャーナリストの内藤國夫氏や隈部大蔵氏などに対する妨害なども含む、きわめて大規模で悪質なものだったのである。
例えば隈部大蔵氏は、西日本新聞社の論説委員をしていたころ、「隅田洋」と名乗り『創価学会・公明党の破滅』という学会批判本を執筆した。
すると、昭和43年9月11日、隈部氏は、当時公明党の副委員長であった北条浩に呼び出され、
「いくらペンネームを用いて学会を批判しようとしても、全国的に張りめぐらされている学会の情報網にひっかからない『虫ケラ』はいないのだ。わかったか」
「よく聞いたがよい。たとえていえば、創価学会は『象』それも巨象だ。これにくらべてお前は1匹の『蟻』だ。創価学会を批判する輩に対しては、たとえ1匹の蟻といえども象は全力をもって踏みつぶすのだ」
と恫喝(どうかつ)されたのだ。
この他、内藤國夫氏に対するものも含め、夜中の脅迫電話や脅迫状など、事件は限りなく拡大したが、たまたま藤原弘達氏に対する妨害が大きく取り上げられることとなったのは、先に述べたように、藤原氏に対する様々な妨害行為の中で、当時の自民党幹事長・田中角栄氏まで担(かつ)ぎ出したことが表面化したからに他ならない。
この、田中角栄氏担ぎ出しについて、当事者である竹入氏は、
●創価学会批判の本が出るというので、私が田中さんに頼んで仲介に動いてもらった(竹入義勝=元公明党委員長『朝日新聞』980826)
と、真相を明かしているが、時の自民党幹事長まで駆り出しての謀略(ぼうりゃく)劇が、社会問題化するのは当然といえよう。
かように、自ら招いた〝災禍(さいか)〟であるにも拘(かか)わらず、『新・人間革命』では、この田中幹事長担ぎ出しの事実にはいっさい触れないばかりか、
「公明党と学会による〝圧力〟は、既成の事実とされ、にわかに、〝政治的大問題〟にされていったのである」(第33回)
と、あたかも「事件」そのものが冤罪(えんざい)であるかのように、事実を書き変えているのである。
また、藤原氏との面会も、「あくまでも要請を伝えたにすぎ」ないなどとしているが、本当にそれだけのことであれば書面1通で事足りようし、もし訪問したとしても、ごく短時間で〝用〟は足りるはずである。
ところが、藤原氏が録音した、秋谷栄之助らとの対話テープは、延々1時間45分にも及び、その内容を全て書き起こした『週刊朝日』(昭和45年3月20日号)の記事は、合計11頁にも及ぶ膨大な量となっているのだ。それを「要請を伝えただけ」だと言い切るのは、どだい無理というもの。
また、『週刊朝日』に掲載された会話は、丁寧(ていねい)な口調ではあるが、
「本当に、今、言ったことを後でくり返して、ああ、おれ誤った、なんて言わないように」
といった、限りなく〝脅迫〟に近い言い回しが使われているのだ。
しかし、それより何より、「本のタイトルが云々」「宗教的内容は云々」「会長のことは云々」と、同じ要求を執拗(しつよう)にくり返し続けること自体、すでに、「要請を伝えた」という域をはるかに超えているというべきである。
『新・人間革命』の伝(でん)でいけば、ミャンマーの軍事政権によるアウンサン・スーチー女史の軟禁なども、「雑音の入らぬ静かな場所で、じっくりと意見交換を行なっている」ことになろう。
<「取扱拒否は自主判断」というが>
―実際は「批判本扱うな」と圧力―
************************************************************
>今回、学会が書籍の取次各社や書店に対して、批判書を扱わぬよう組織的に圧力をかけたと、盛んに喧伝(けんでん)されている。
出版業務に携(たずさ)わるメンバーのなかに、取次店や書店で批判書の非道さを訴え、取り扱いの配慮を要請した人はいたようだ。
しかし、その書籍を取り扱うかどうかは、本の内容や出版社の業績等から、取次各社が独自で判断したはずである。
特定の宗教団体や政党を激しく中傷した書籍や、業績のない出版社の本の取り扱いに対して、取次各社が慎重になるのは当然であろう。(『新・人間革命』「烈風」)
>また、学会の圧力で新聞広告や電車の中吊り広告の扱いも断られたと言っているが、それは、各社が広告倫理規制などに基づいて判断したものであろう。(『新・人間革命』「烈風」)
>そもそも、衆院選挙前に、学会と公明党を攻撃する、選挙妨害の疑いさえある書籍の広告を、不偏不党をうたった大新聞等が扱うなど、考えられないことではないか。(『新・人間革命』「烈風」)
------------------------------------------------------------
〝個々の学会員による働きかけはあったかもしれぬが、書籍取次業者も、大手新聞各社も、自己判断によって取次や広告掲載を自粛した〟との言い分だが、組織的に圧力をかけた事実がある以上、この主張は根底から崩れている。
『フォーラム21』誌7月1日号に、当時、学会職員で、実際に書店に圧力をかけに行った人々へのインタビュー記事が載っているので、紹介しよう。
――岩崎(文彦氏=元・聖教新聞社出版局勤務)
私は、業務命令で書店に行かされました。
たしか全員で19名だったと思います。本が店頭に並ぶ少し前に、各部門から選抜されたメンバーが急遽(きゅうきょ)、集められました。聖教新聞社の広告局、業務局(新聞販売部門)、出版局(書籍販売部門)、潮出版社からも来ていました。
場所は聖教旧館の隣にあった業務局が入っていた建物の2階仏間で、私は出版局からの選抜です。責任者は出版総局長だった横松昭、出版局次長だった青柳清が現場の指揮をとっていました。
そこで聞かされたのは、こんな話です。「藤原弘達が『創価学会を斬る』という本を出す。創価学会を批判するとんでもない本だ。書店を回ってそれを押さえろ」。書店での口上も指示されました。「この本を、ここにある棚から中にしまってください。そうしてもらえなければ、『人間革命』などの扱いをしません」。『人間革命』は書店にとって売れ筋の本でしたから、十分圧力になると考えたのでしょう。そして最終的には、「創価学会を敵に回すのか」と。そこまで圧力をかけろ、と言われたんです。――
また同誌には、『創価学会を斬る』の出版元の、(株)日新報道代表取締役で、当時、『創価学会を斬る』を担当していた遠藤留治氏へのインタビューも掲載されている。
遠藤氏はその中で、書籍取次店への学会の圧力のすさまじさを、次のように語っている。
――『創価学会を斬る』を担当していた遠藤留治
日販、東販という大手書籍流通会社をはじめ、のきなみ拒否です。「取り扱えない」というので、「なぜだ」「どうして」と理由を聞くと、誤魔化していましたが、そっと創価学会の圧力であることを教えてくれる業者もありました。結局、書籍の配本契約を結んでいた11社のうち、初版の配本を請け負ってくれたのは栗田書店1社だけという悲惨な状況でした。(中略)
藤原弘達氏が創価学会・公明党による言論出版妨害の事実を明らかにする以前、私も『朝日新聞』や『読売新聞』など、全国紙の記者や編集幹部に会って、創価学会・公明党がこんなひどいことをしていると事実を説明しました。
ところが、彼らはこの問題を全く扱おうとはせず、政治問題化してから初めて扱うようになったんです。このマスコミの怠慢(たいまん)には本当に失望し、怒りを覚えました。
今日も、創価学会の莫大な広告費や『聖教新聞』の印刷費、購読部数、視聴率などの前に、新聞・テレビなどの巨大メディアは屈し、創価学会問題を積極的に報じようとはしませんが、当時から彼らは、勇気とジャーナリズム精神を喪失していた、と言わざるをえません。――
これらの証言で明らかなように、池田創価学会は、職員に「口上」まで指示して、組織ぐるみで書店などに圧力をかけ、その圧力に屈した書籍取次店は、普段取り引きのあるところでさえ、取次ぎを拒否してきた、というのが「事件」の真相なのだ。
ここでもまた、池田創価学会は事実を改ざんしているのである。
<「著者脅迫は学会陥れの謀略」!?>
―学会員の妨害行為は今もなお―
************************************************************
膨大(ぼうだい)な数の抗議の電話や手紙が殺到し、学会から圧力をかけられたとされていることはどうか。
学会員の怒りは、確かに激しいものがある。自分たちの団体が、「狂信者の群れ」「ナチス」「愚民化」などと罵倒(ばとう)されれば、普通の神経なら、誰でも怒りを覚えるであろう。また、一部に抗議する人が出るのも当然である。(中略)
それにしても、伸一が腑(ふ)に落ちないのは、いやがらせや脅迫電話、脅迫状が相次いだと言われていることである。
もし、喧伝されたように、学会員が、脅迫じみた言動をとれば、さらに学会に非難が集中することは自明の理である。
そんな学会を貶(おとし)めるようなことを、あえて学会員がするとは、どうしても考えられなかった。
脅迫電話や脅迫状があったとするなら、学会への反発や敵意を高めさせるための謀略かもしれない。
しかし、困ったことには、それを証明する手立てはなかった。(『新・人間革命』「烈風」)
------------------------------------------------------------
果たして、学会員の抗議とは、どのようなものだったのだろうか――。
再び(株)日新報道の遠藤氏へのインタビューから引用する。
――『創価学会を斬る』を担当していた遠藤留治
「この日本をどうする」第1巻の『日本教育改造法案』を昭和44年8月に出版した際、国鉄(現JR)、私鉄の各線に中吊り広告を出したんですが、その広告の左端に、次作として『創価学会を斬る』の出版予告を載せたんです。抗議電話が始まったのは、この出版予告を出した直後からでした。
会社にいると電話がジャンジャンかかってくる。それは『日本教育改造法案』についての問い合わせ電話ではなく、ほとんどすべてが『創価学会を斬る』についてのものでした。「いったいどういう内容なんだ」「いつ出版するんだ」という探りの電話から、「出版をやめろ」とか、「ぶっ殺すぞ」「地獄に堕(お)ちるぞ」という脅迫電話まで、ひっきりなしでした。もちろん名前は名乗りません。一方的に怒鳴りまくった上で電話を切る、というパターンが延々と続きました。
また、この抗議電話とともに、舞い込んだのが抗議の葉書や手紙でした。段ボール何箱分になったでしょうか。とにかくもの凄い数でした。
(藤原弘達氏宅に対しても)それはひどいものでした。やはり段ボール箱で何箱にものぼったんじゃないでしょうか。電話での脅迫もひどいものでしたので、警察がそれとなく藤原弘達氏のお子さんなど家族の警備をしたほどでした。
ですから藤原弘達氏は身の安全を図るため、都内のホテルを転々として『創価学会を斬る』の執筆を続け、私たちも移動しながら編集作業を続ける有り様でした。
なお、この抗議電話や葉書は出版後もますますエスカレートし、内容もひどいものでした。――
車内吊りの予告広告を出しただけで、抗議の電話や郵便が殺到した、というのだから、これぞまさに「出版妨害」ではないか。「罵倒され」たから「普通の神経なら、誰でも怒りを覚え」た、などというものではない。
しかも、言うに事欠いて
「脅迫電話や脅迫状があったとするなら、学会への反発や敵意を高めさせるための謀略かもしれない。しかし、困ったことには、それを証明する手立てはなかった」
とは。
ここで一いち検証はせぬが、相手側に「証明する手立て」さえなければ、どんな嘘でも平気で主張する、というのが、池田創価学会の恒常(こうじょう)的体質ではないか。盗人猛々(たけだけ)しいとは、このことだ。
以上、『新・人間革命』が行なった、愚劣な歴史の改ざんを糾弾したが、そもそも1番の問題は、昭和45年5月3日の、「事件」に対する池田の謝罪講演以降も、創価学会の犯罪体質がいっこうに改善されていない、ということである。
その証拠に、当慧妙編集室に対しては、今でも、電話や郵便物、ファックスによって、〝いやがらせ〟や〝脅迫〟まがいの行為が、執拗(しつよう)にくり返されているのだから――。
池田創価学会が、いくら過去を隠蔽(いんぺい)することに躍起(やっき)になろうとも、それは全く無意味だということに気付くべきである。